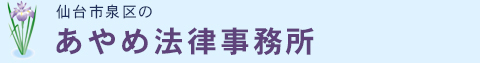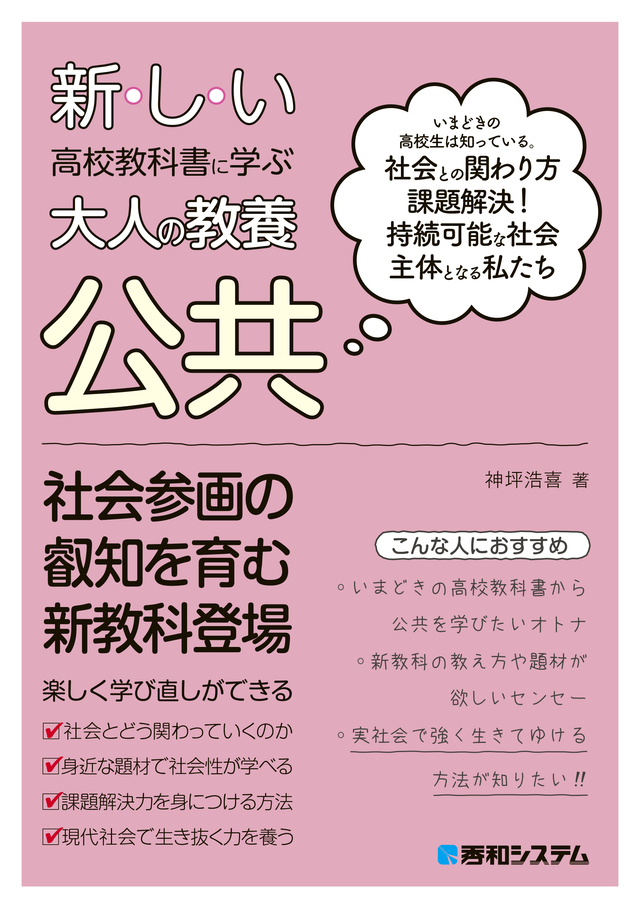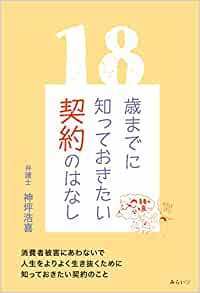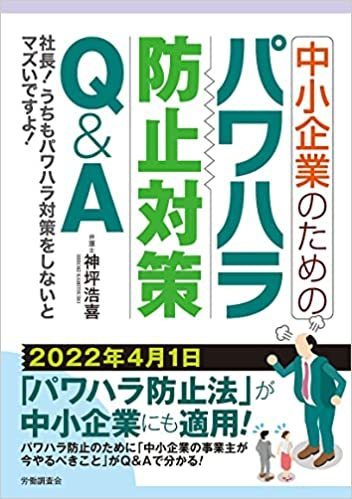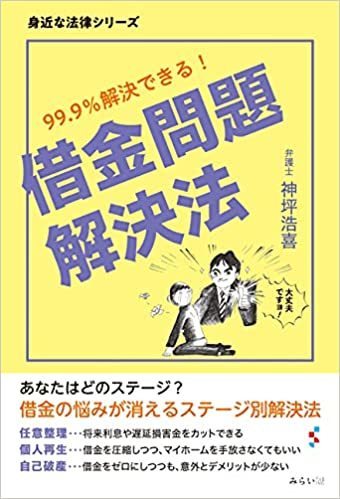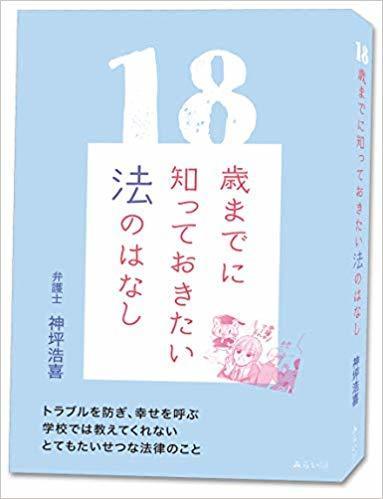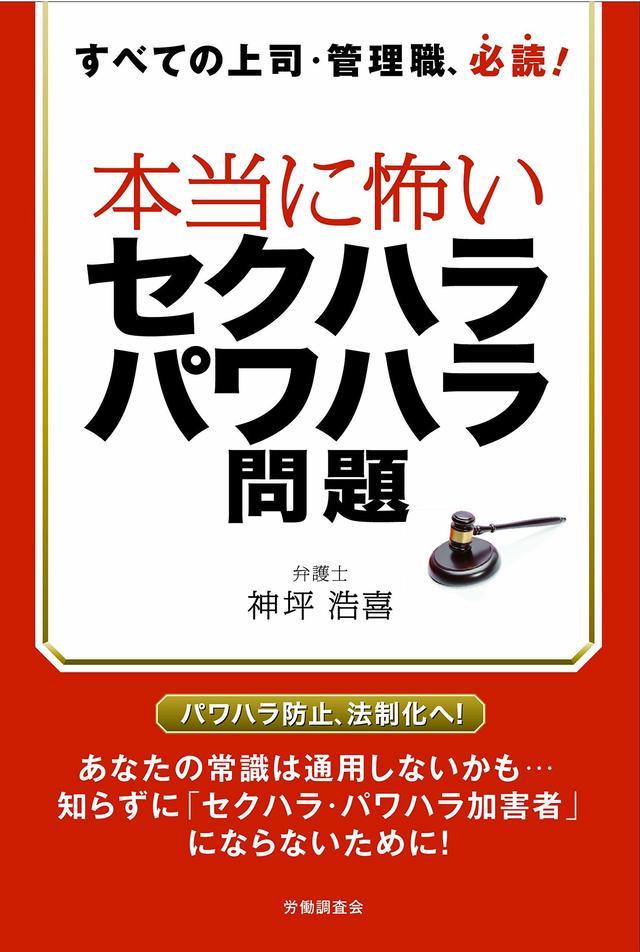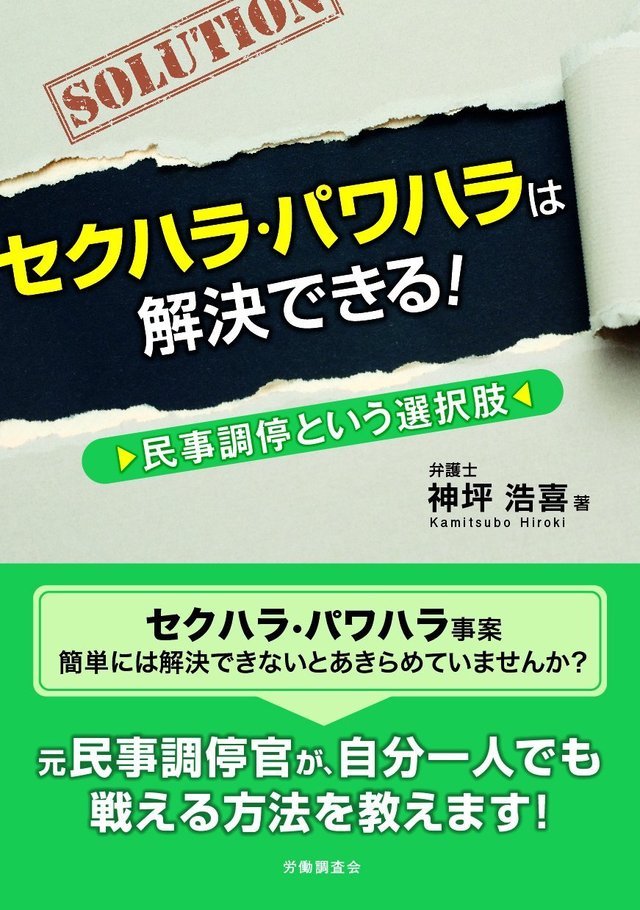宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
<お電話での相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後0時20分
午後1時20分から午後5時15分まで
メールでは24時間受付
配偶者居住権が新設されました(令和2年4月1日施行)
弁護士の神坪浩喜です。
相続法改正の目玉ともいえる「配偶者居住権の新設」が令和2年4月1日から施行されました。
配偶者居住権は、高齢化社会の進展や家族のあり方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み、配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮を行うものです。
この制度を活用することによって、場合によっては、のこされた配偶者は、自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになります。
これまでは、被相続人の遺産が、不動産のみか、ほぼ不動産しかない場合には、不動産を取得する配偶者は、他の財産(預貯金等)を受け取れなくなってこれからの生活費がない、さらには、他の相続人に対して代償金を支払う必要をせまられ、結局不動産を売却しなければならなくなる・・。
夫としても、自分が逝った後、妻に住む場所と生活費も残してあげたい・・・。
そこで方策として、改正法によって「配偶者居住権」という権利を創設しました。
これは、不動産を「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に権利をわけるものです。
通常、不動産に居住するためには、何らかの権利を持っている必要があります。
まずは、所有権
次に、借りて住む権利(使用貸借、賃貸借)
何も権利がなければ、「不法占拠」となってしまい、住み続けることはできません。
住めるためには、何らかの権利が必要です。
所有権が、一番安定していますが、不動産は所有権は高額なものになりがちです。
借りることは、安くあるいは無償で借りることができるかもしれませんが、所有者との契約(同意)が必要になってきます。相手との関係が気まずければ、難しくなってきます。
そこで、「配偶者居住権」という権利を創設し、安定して居住できるとともに、その取得のための価値が、所有権より安くできるというようにしたのです。
配偶者のこれまでの居住を守りつつ、生活費を確保するということが、ねらいです。
事例で見ていきましょう。
例)夫(父)の遺産
2000万円の自宅不動産(土地・建物) 預貯金2000万円 計4000万円
相続人は 妻(母)と子 相続分は2分の1ずつ
これまでは、妻が2000万円の不動産を取得すると、預貯金はもらえませんでした。
つまり、妻(母)の生活費がなくて困ることになります
そこで、不動産の価値をわける。配偶者居住権と負担付き所有権をわける。住み続けたい妻が配偶者居住権を取得します。
配偶者居住権分1000万円 負担付き所有権1000万円
そうすると預貯金が2000万円あれば、それを折半して、1000万円の預金が妻にも残ることになり、生活費が確保できるのです。
お父さん(85) お母さん(80) 二人で住んでいた。長男(55)は独立して家を出て、家庭をもっている。
そんな場合、お父さんが亡くなったとき、お父さんと一緒に住んでいた場合、お母さんは、遺産分割によって配偶者居住権を取得することで、お母さんがなくなるまで、一定期間、その家に住むことができるようになります。
そして、お父さんの遺産に預貯金があれば、その半分も、お母さんの手元にのこって、安心。
というわけです。
遺産分割協議のときだけではなく、被相続人が遺贈によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
なお、居住用不動産以外に預貯金がある程度あれば、居住用不動産を配偶者の所有にしても預貯金の分配によって、配偶者の生活費は確保できるでしょう。
受取人を配偶者とする生命保険をかけることで、生活費を確保するやり方もあります。
連れ添った配偶者が、自分が死んだあとに、困らないように、できることはやっておきましょう。
※配偶者短期居住権
今回の改正では、上記の配偶者居住権のほかに、配偶者が、被相続人の財産に属した建物に、相続開始時(被相続人が亡くなったとき)に、無償で居住していた場合には、遺産分割によってその建物が誰に帰属するかを確定するまで、あるいは相続開始から6か月までの、いずれか遅い日までは、無償でその建物に住むことができるという「配偶者短期居住権」を新設しました(民法第1037条)。
法律相談のご予約

お気軽にご相談ください。
お電話でのご予約はこちら
022-779-5431
相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで
メールでの受付は、24時間行っております(折り返しのご連絡は、基本的に上記受付時間となります)。
借金、相続、離婚、交通事故、不貞慰謝料の相談料は30分以内無料です。その他の事件は、30分あたり5500円です。
※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。
※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。
※取扱い地域
仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域
無料法律相談のご予約
コラム
- バーガー国ものがたり~3つのアイデア:自然権、社会契約、法の支配
- 他人と比べないこと(R3.11.15)
- 生きがいについて(R2.11.23)
- 所有権絶対の原則!(R2.4.6)
- 長男の妻の労苦は報われるのか?(R2.4.2)
- 配偶者居住権が新設されました(R2.4.1)
- パワハラをしないためには知識が必要です!(R2.3.25)
- こども六法(R1.9.24)
- 国民主権って何だろう?(R1.7.15)
- 裁判官はどのように判断しているのか?(R1.7.6)
- 自分の主観と相手の主観とはズレているもの(R1.6.30)
- 本当に怖いセクハラパワハラ問題(R1.6.22)
- 愛の本2 自分以外の人は全て他者(H31.2.10)
- 愛の本 他者との〈つながり〉を持て余すあなたへ(H31.2.3記)
- 自分の一番の味方は自分(H31.1.21)
- 友だち幻想3 人生の苦味・うま味(H30.9.9)
- 対人距離がわからない(H30.8.6)
- 正義とは他者に対する公正さ(H30.7.15)
- 人間関係に悩んだら、とりあえず「登場人物」を紙に書きだす(H30.6.12)
- 友だち幻想2 距離の感覚(H30.5.29)
- 友だち幻想 人と人のつなばりを考える①(H30.5.14)
- 主観的に大切なこと、客観的に重要なこと(H30.5.3)
- 自己開示の効用(H29.12.23)
- 人生は思うようにはならないもの(H29.9.21)
- 正義って何?~反転可能性テスト(H29.9.16)
- 悩んだら、とりあえず散歩(H29.6.25)
- 自分に価値があると思えるために2(H29.4.27)
- 自分に価値があると思えるために(H29.3.5)
- 3人のレンガ職人(H28.9.26)
- よく生きるために働くということ(H28.9.18)
- 弘前の桜(H27.5.8)
- 取引先破綻の商品引き上げについて
- ずっと運の悪い人はいませんよ。
- 第○回の調停を始めます! (H26.8.30)
- 複数のスポーク
(H26.8.14) - 嫉妬心とのつきあい方(H26.7.27)
- 本当は仲直りがしたいのに (H26.6.15)