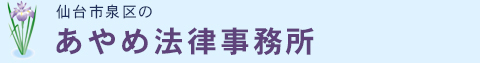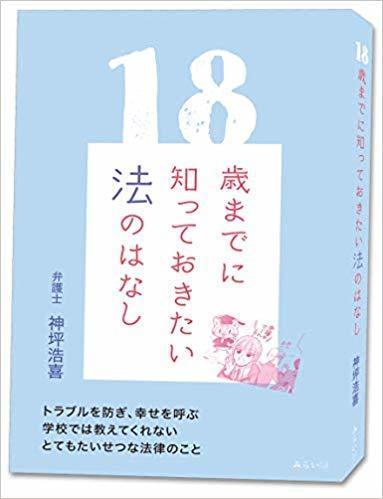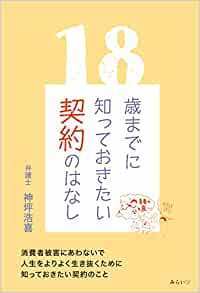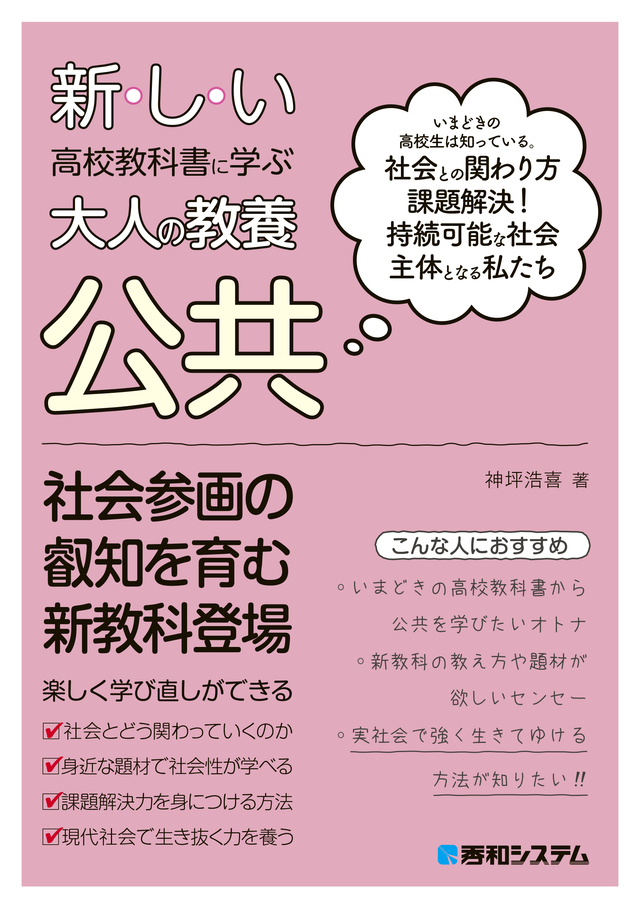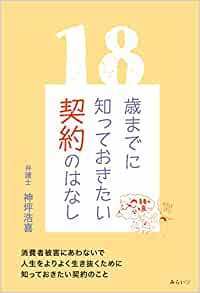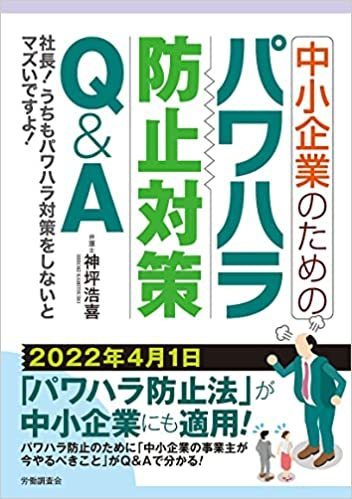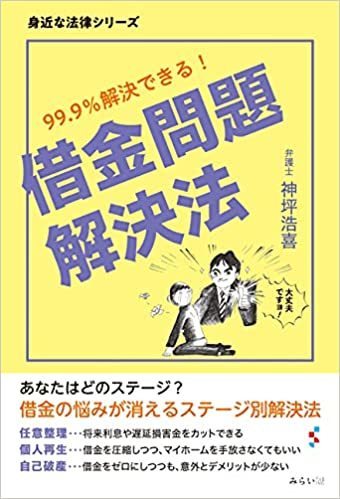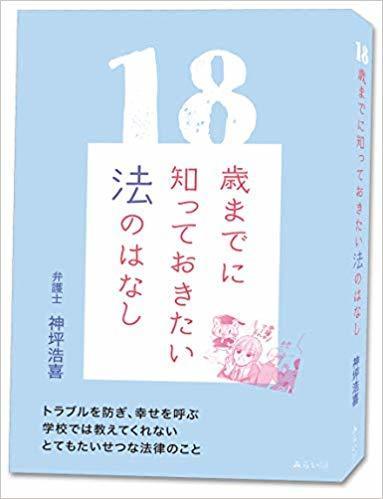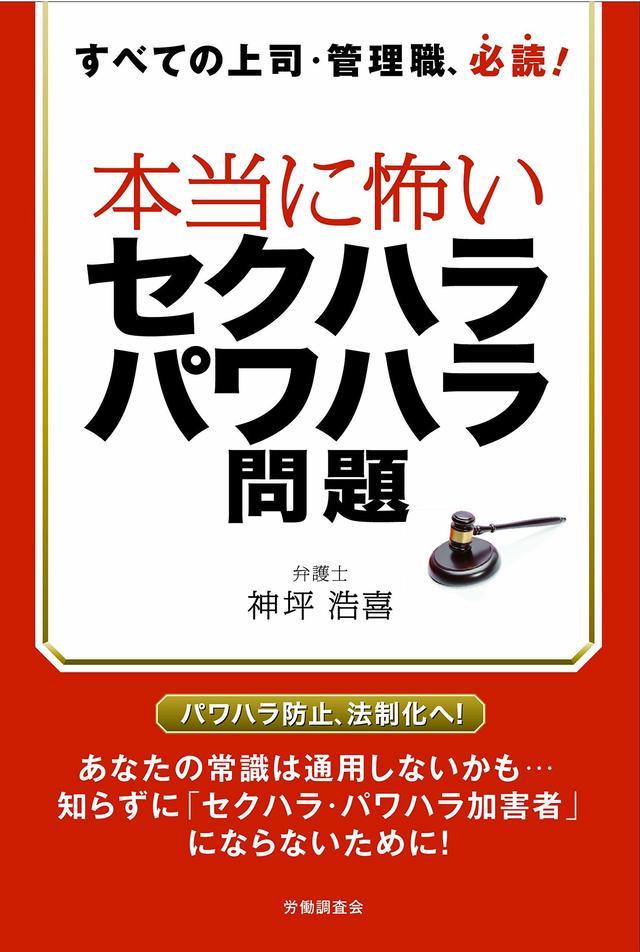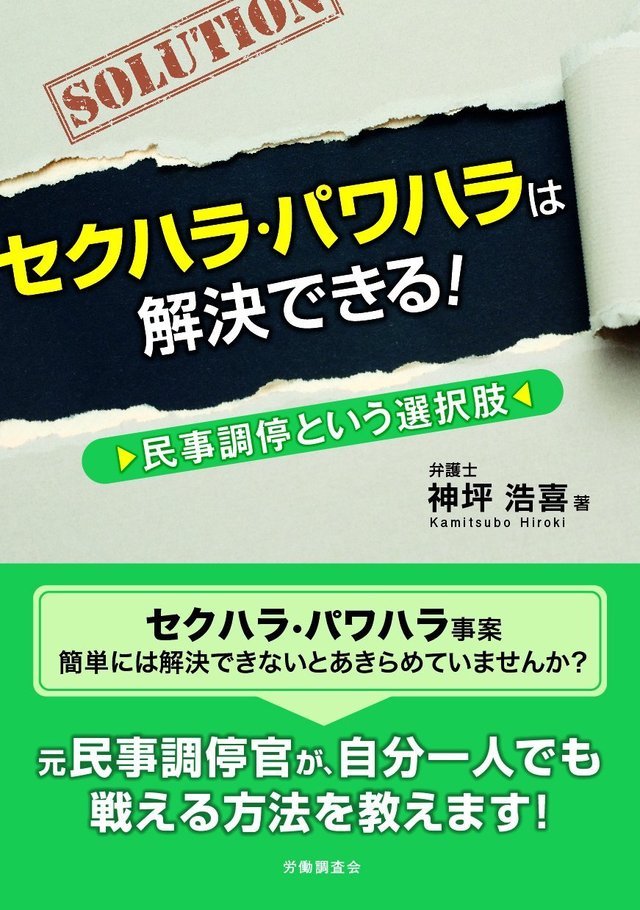宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
<お電話での相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後0時20分
午後1時20分から午後5時15分まで
メールでは24時間受付
所有権絶対の原則!
こんにちは。
弁護士の神坪浩喜です。
「18歳までに知っておきたい法のはなし」(みらいパブリッシング)は、もとの原稿約15万字あったところ、紙面の都合で、4万字以上削りました。
契約のはなしの後に、私法の大原則である「所有権絶対の原則」について書いていましたが、これも泣く泣く削りました。とても大切な原則なので、ここで、紹介いたしますね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
所有権絶対の原則
(1)自分の物、他人の物って何だろう?
契約は、価値の交換であるといった。売買契約なら、お店(売主)は、物を渡すかわりに、代金をもらう。買主からすれば、代金を払うかわりに、商品を受け取る。売主と買主の間に、そのような合意があり、それに拘束される。
売買契約によって価値を移転させることができるのは、お店がその商品の所有者であることが前提になっている。
その商品という価値を持っているから、誰かに売ることができるのだ。
所有していることって、どういうことだろう。
自分のものってどういうことだろう。
君の机の上に、国語辞典がある。それは、君が書店から買ったものかも知れないし、お父さんからもらった物かもしれない。君は、その辞書が自分のものであると思っている。
しかし、自分のものってどういうことだろうか。
君は、この辞書を使うことができる。線を引くこともできたり、折り曲げたりすることもできる。辞書本来の使い方ではないが、枕にすることもできる。
また、君は、その辞書を友達に貸すことができる。辞書なら普通はお金をとらないでタダで貸すだろうが、1日100円で貸すと友達と決めて貸すこともできる。
そして、君は、この辞書を誰かにあげたり、売ったりすることもできる。新しい辞書を買ったのでいらなくなったとして、捨てることも可能だ。
また、誰かに、辞書を取られたら「その辞書を返してくれ」という権利もある。辞書が汚されたら、損害賠償を求める権利もある。
「所有権」があるというのは、目的となった物に対して、「自分の意思に従って、自由に、排他的に、使用、収益、処分する権利」があるとされる。「所有権絶対の原則」とよばれ、所有権には強い権利がある。
所有権があるということは、イメージとしては、物に対する価値をガチッと把握しているということだ。
お店から何か商品を買おうとしているときには、お店の物だという信頼があるからだ。今、売主に所有権があって、売主がその商品に対して「排他的に、使用、収益、処分する権利」があると信じているからこそ、お金を出して、商品を買おうと思うのだ。
もし、その商品について、売主に権利がなかったり、あいまいな権利だったり、制限されている権利だったら、怖くて買えないだろう。
つまり、契約(=価値の交換)をすることができなくなる。
所有権が強く保障されていることが前提となって、契約(=価値の交換)も、安心してできるわけだ。つまり、取引が活発となる。
所有権の保障は、契約自由の原則とあわせて、資本主義経済を発展させたんだ。
※相手は本当に所有者なのか?
誰かから、高価な物を買おうとする場合、本当にその人が所有者なのかを確認することが重要だ。お店から食料品や日用品を買うときは、お店で売っている以上、お店に所有があると思って間違いがないが、例えば、ネットで、中古自転車を購入しようとする際に、本当に売ろうとしている人の所有なのかは、確認しよう。盗んできたものを販売していたりすることもあるからだ。
そして、自動車やバイクを購入する際には、車検証を確認する。車検証を見れば、誰の所有かがわかる。不動産(土地や建物、マンション)は、不動産登記事項書を確認すれば、誰の名義になっているかがわかる。
詐欺師は、車検証や不動産登記事項証明書を「偽造」してくることもあるから、注意が必要だ。不動産登記事項証明書は、だれでも取り寄せることができるから、取引する際には、自分で確認しておくのがよいだろう。
(2)所有者なら何でもできるか?-権利の濫用は許されない
所有権は「所有権絶対の原則」と強い保護が与えられる権利だ。強く保障されているから、物を売ったり、買ったりすることができる。
しかし、原則には例外があるように、所有権といえども、全く制限がないわけではない。
ここは、自分の土地だからといって、当然に超高層ビルを立てていいわけではない。建物の高さ制限が決められていれば、それに従わなければならない。
高速道路をつくるといった一定の公共事業のために必要とされるときは、一定の補償(土地の代わりのお金をもらうこと)で、国が土地を収用(取り上げること)もある。
「宇奈月温泉事件」という大学法学部生は必ず習う有名な裁判例がある。昭和10年に、大審院という今の最高裁判所で出された古い判決だ。
宇奈月温泉というのは、富山県にあって、黒部トロッコ鉄道も近い温泉なのだが、昭和のはじめ、温泉の引っ張ってくる管の土地をかった人が、金儲けをたくらんで、引湯管のある土地の一部を安く買って、引湯管所有者に対して、土地の所有権に基づいて、引湯管を撤去するか、この土地を時価数十倍のべらぼうな金額で買い取れといった。引湯管所有者がそれを拒否すると、土地所有者は撤去をせまって裁判を起こした。
・土地所有者は、その土地を何かに使う予定はなかったし、傾斜地で使いようもなかった。撤去を認められなくても大した損害を被るわけでもない。
・他方で、この土地を使えずに引湯管を撤去しなければならないとすると、引湯管所有者は、大きな損害を被ってしまう。
・土地所有者は、その土地を安く買って、引湯管所有者に対して、べらぼうに高い金額で買い取りを迫っていた。
このような事情があった。
「所有権絶対の原則」からすると、たしかに土地所有者には、妨害排除請求権という権利があり、撤去が認められそうだ。
でも、これっておかしいよね。
そこで、裁判所も、土地所有者の所有権に基づく撤去請求は「権利の濫用」として、その権利行使は制限されると言ったのだ。所有権があるからといって、なんでもできるわけではないぞ、と釘をさしたわけだ。
「所有権が侵害されてもこれによる損害がいうに足りないほど軽微であり、しかもこれを除去することが著しく困難で莫大な費用を要するような場合に、不当な利益を獲得する目的で、その除去を求めるのは、権利の濫用にほかならない」としたのだ。
自分の所有地だからといって、他の人や公共の利益を不当に害するような利用や権利行使は認められないんだね。
判決当時は、なかったけれど、現在は民法1条3項で「権利の濫用は、これを許さない」と明文化されている。
ただ、「権利の濫用」という所有権の行使の制限は例外的なものであり、あくまで原則は、所有権を侵害されたら、その回復を請求できるということはおさえておいてほしい。
所有権絶対の原則は、強く保障されているのだ。
法律相談のご予約

お気軽にご相談ください。
お電話でのご予約はこちら
022-779-5431
相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで
メールでの受付は、24時間行っております(折り返しのご連絡は、基本的に上記受付時間となります)。
借金、相続、離婚、交通事故、不貞慰謝料の相談料は30分以内無料です。その他の事件は、30分あたり5500円です。
※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。
※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。
※取扱い地域
仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域
無料法律相談のご予約
コラム
- バーガー国ものがたり~3つのアイデア:自然権、社会契約、法の支配
- 他人と比べないこと(R3.11.15)
- 生きがいについて(R2.11.23)
- 所有権絶対の原則!(R2.4.6)
- 長男の妻の労苦は報われるのか?(R2.4.2)
- 配偶者居住権が新設されました(R2.4.1)
- パワハラをしないためには知識が必要です!(R2.3.25)
- こども六法(R1.9.24)
- 国民主権って何だろう?(R1.7.15)
- 裁判官はどのように判断しているのか?(R1.7.6)
- 自分の主観と相手の主観とはズレているもの(R1.6.30)
- 本当に怖いセクハラパワハラ問題(R1.6.22)
- 愛の本2 自分以外の人は全て他者(H31.2.10)
- 愛の本 他者との〈つながり〉を持て余すあなたへ(H31.2.3記)
- 自分の一番の味方は自分(H31.1.21)
- 友だち幻想3 人生の苦味・うま味(H30.9.9)
- 対人距離がわからない(H30.8.6)
- 正義とは他者に対する公正さ(H30.7.15)
- 人間関係に悩んだら、とりあえず「登場人物」を紙に書きだす(H30.6.12)
- 友だち幻想2 距離の感覚(H30.5.29)
- 友だち幻想 人と人のつなばりを考える①(H30.5.14)
- 主観的に大切なこと、客観的に重要なこと(H30.5.3)
- 自己開示の効用(H29.12.23)
- 人生は思うようにはならないもの(H29.9.21)
- 正義って何?~反転可能性テスト(H29.9.16)
- 悩んだら、とりあえず散歩(H29.6.25)
- 自分に価値があると思えるために2(H29.4.27)
- 自分に価値があると思えるために(H29.3.5)
- 3人のレンガ職人(H28.9.26)
- よく生きるために働くということ(H28.9.18)
- 弘前の桜(H27.5.8)
- 取引先破綻の商品引き上げについて
- ずっと運の悪い人はいませんよ。
- 第○回の調停を始めます! (H26.8.30)
- 複数のスポーク
(H26.8.14) - 嫉妬心とのつきあい方(H26.7.27)
- 本当は仲直りがしたいのに (H26.6.15)