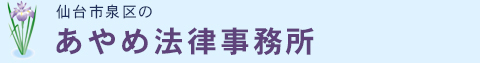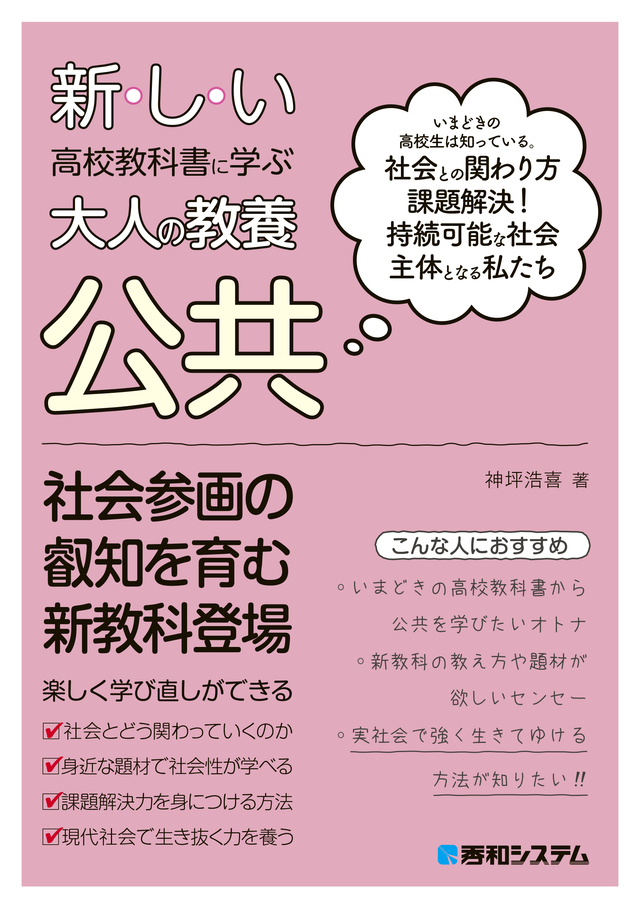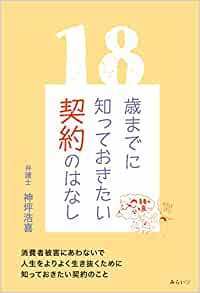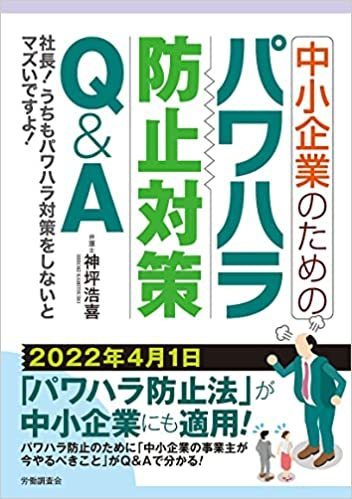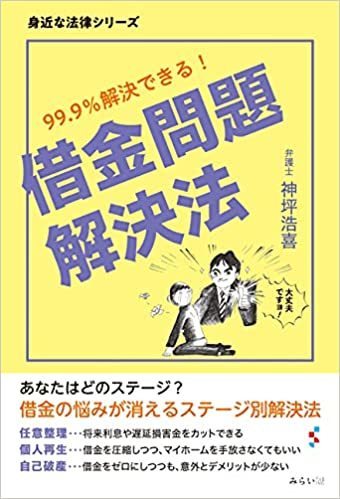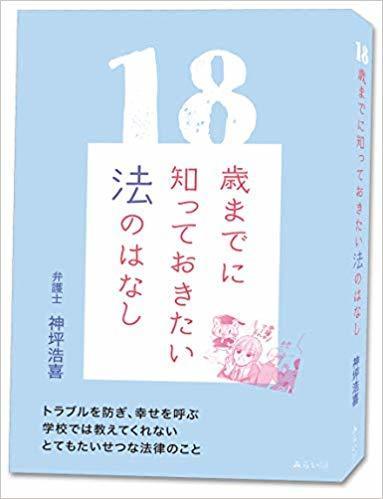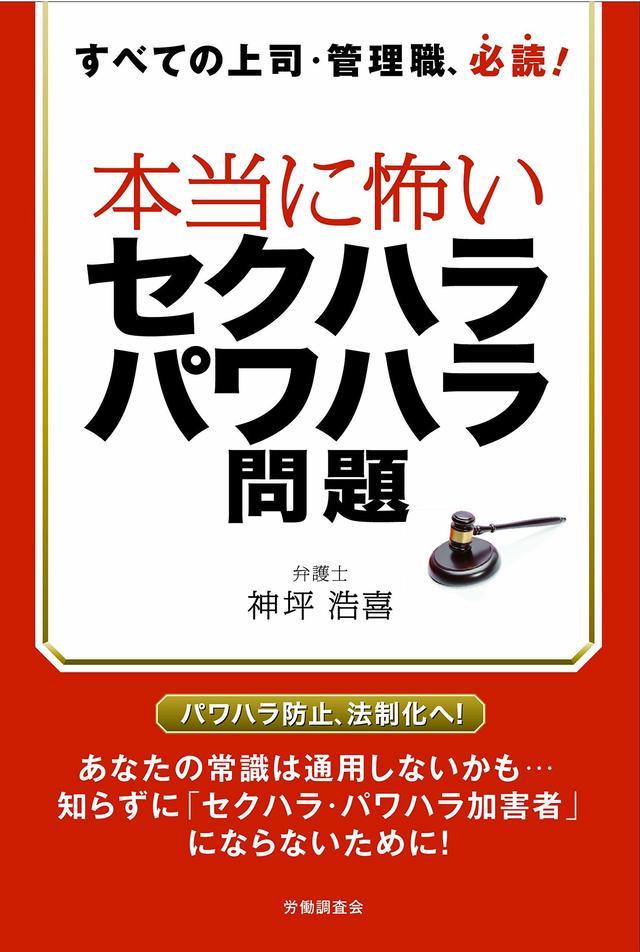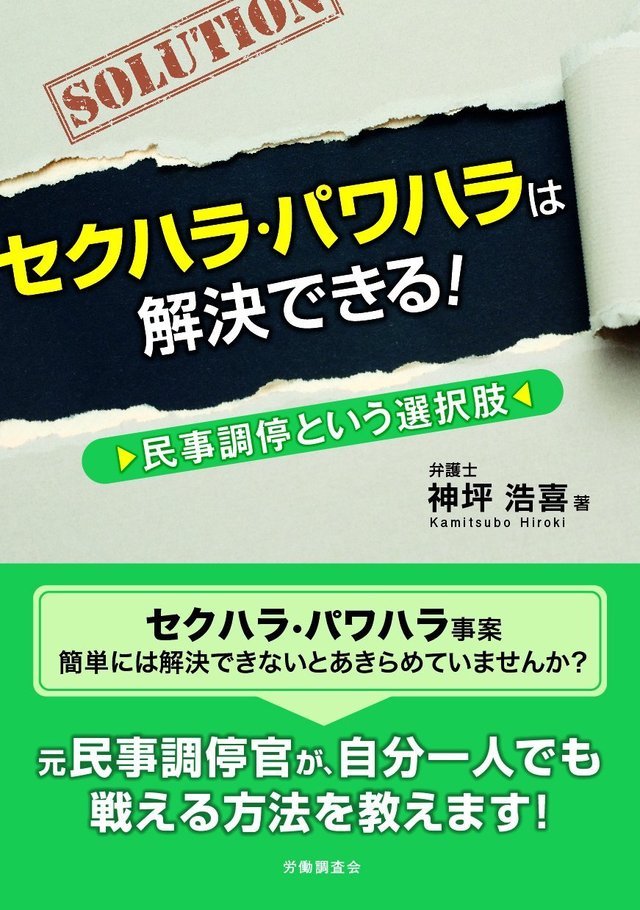宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
<お電話での相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後0時20分
午後1時20分から午後5時15分まで
メールでは24時間受付
相続問題(遺言・遺産分割協議・遺留分)でお悩みの方へ
父親の遺産分割で、兄弟間でもめている・・・。
遺産分割調停をおこされたが、どうすればいいのか・・・。
父親の遺言書が見つかったが、どうすればいいのだろう・・・。
亡くなった父親が多額の借金を抱えていた・・・。
このような相続問題でお悩みの方は、あやめ法律事務所にお気軽にお電話(022−779−5431)ください。当事務所では、相続問題の解決に力を入れております。

弁護士・相続診断士の神坪浩喜です。
人は、公平に取り扱われないと、悲しみ、時に怒りを感じるものです。相続問題の案件を多く扱っておりますと、人は「公平」に扱われたいと願っているということ、公平であると感じるのは人それぞれであること、そして公平であることの難しさを感じます。
単純に機械的に分ければ公平というものでもありません。人にはそれぞれの事情があり、思いがあります。
被相続人(親)との関わり合い、親の気持ち、自分の事情・・・いろいろな問題が複雑にからみあっています。相続問題は、誰もが一生に何度かぶつかる人生の大問題です。
そのとき、他の相続人の主張が公平でないと感じたり、できれば多く遺産をもらいたいと思うのは、人情であり、また現実的に金銭が必要なタイミングであったりします。
人は、相続でこれまで思いもよらなかった心理的葛藤に直面します。
それまで仲がよかった兄弟で、親の相続問題をきっかけに、骨肉の争いとなり、絶交となってしまうこともあるのです。
相続問題では、被相続人とのそれぞれの関係、相続人間の関係、相続人の経済状況、相続財産とその性質と評価、分割方法、税金問題、相続人間の交際、葬祭など、たくさんの要素が絡み合う複雑な事態が生じます。
法律は、「公平」であるように整備されていますが、実際の相続問題では、法律では割り切れない難しさを持ち、民法でも例えば「遺産の分割は、遺産の属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」として、具体的な調整は、相続人間の話し合いに委ねているところです。
このように、具体的な事案においては、その事案特有の事情を織り込みながら、「公平」な分配になるように、当事者間で話し合いをするのですが、なかなかこれが難しいものです。この事案において「公平」な解決は何なのか、公平には取り扱われたい、自分の希望は「公平」なのか、相手の主張は「公平」なのか、その判断は難しいところです。
公平で納得できる遺産分けのために、円満な相続のために、ぜひ弁護士にご相談ください。
相談のご予約は、022−779−5431までお電話か、法律相談フォームで。
法律相談フォームでのお申込みの場合は、相談日時調整のため、折り返しこちらからお電話を差し上げます。
ご相談のあと、必要に応じて遺産分割協議の示談交渉や調停を、よろしければご依頼いただくことになります。
あやめ法律事務所の弁護士に、遺産分割協議交渉、調停をご依頼されると
- 法律と具体的事情にそった適正な分与を獲得できた
- 兄弟(その代理人弁護士)と交渉するストレスから解放された
といった効果が期待できます。
まずは、ご相談から。お気軽にお電話ください。
遺言、遺産分割の弁護士費用(税込み)
遺言書作成
| 定形的なもの | 11万円 |
|---|---|
| 非定形的なもの | 11万円に、難易度に応じて加算いたします。 |
公正証書遺言の場合には、公証人費用の実費が別途かかります。
相続放棄
| 相続放棄 | 一人あたり4万4000円 一人のみの場合は、5万5000円 |
|---|
戸籍取り寄せ費用、申し立て費用等実費が別途かかります。
遺産分割協議サポート
弁護士が表だって交渉すると角が立つというような場合に、交渉自体はお客様ご本人にやっていただき、背後で弁護士が交渉や協議書作成についてお客様にアドバイス、サポートするものです。
| 着手金 | 22万円以上 |
|---|---|
| 報酬 | 取得できた遺産額の3%以上 |
遺産分割協議・調停・審判事件
弁護士がお客様の代理人となって、相手方との交渉や裁判上の活動を行います。
| 着手金 | 33万円以上 |
|---|---|
| 報酬 | 取得できた遺産額の5%以上 |
相続人の人数や相続財産の額、事件の難易度により協議によって決めさせていただきます。

ある人が亡くなると、その財産(遺産)は相続人の所有になります。相続人が複数いるときには、相続人間で「遺産分割」という問題が生じてきます。
「遺産分割」は、遺言によって分割の定めがあればそれに従います。遺言がなければ、共同相続人の分割協議により行います。
その際、相続人間でもめることも少なくありません。その場合、家庭裁判所での遺産分割調停や審判という手続きで遺産の分割を行うことになります。
現在相続人間で遺産分割でもめて困っている方はもちろんのこと、将来もめないか不安な方、将来もめないために何をしておけばいいのかわからない方は、どうぞお気軽にあやめ法律事務所までご相談ください。
以下は、多くよせられる相談例です。
- 遺産を同居している長男に多く譲りたいがどうすればいいの?
- 相続人は、誰になるの?
- 相続人ではないが、世話になった方に、遺産を譲りたいがどうすればいいの?
- 遺言ってどのように書けばいいの?
- 相続分って、どうなっているの?
- 遺留分って、どういうものなの?
- 借金も相続しなければならないの?相続放棄って何?
- 遺産分割協議のやり方はどうすればいいの?
- 遺産に何があるか分からない。どのように調査すればいいの?
- 被相続人の預金を引き出したいがどうすればいいの?

あんなに仲がよかった兄弟が、親の相続に直面して、いさかいが生じることもあるのです。
例えば、長男が親と同居し、次男が家を出て独立している時に、父親が亡くなったケース。
法定相続分に従えば、どちらも同じということになります。
しかし、親と同居して、親の面倒や介護をしてきたと思う長男からすると、家を離れていった次男と同じ分割というのは、納得がいかないこともあるでしょう。
逆に、家を離れていった次男は、親と同居している長男が苦労していることを知らず、逆に親からいろいろ援助してもらっていると思ったりして、長男が自分より多く財産をもらえることが納得できず、自分は、当然相続分どおりの権利を主張する!といったりします。
親としては、こんな事態を防ぐためには、元気なうちに、遺言書(できれば公正証書遺言)を書いておくことが大切です。
遺言書には、法律上要件が定められており、その要件を満たしていないと遺言書は無効となり、そのことが新たな争いの原因ともなりかねません。また、遺言書にどのような条項を盛り込むべきなのか、どのような表現にしておくといいのか等もなかなか難しい問題です。
そこで、遺言書の作成にあたっては、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
遺言についての相談も行っておりますので、お気軽にあやめ法律事務所
(022−779−5431)までご相談ください。
Q:「相続させる」という遺言書を書いた遺言者より、先にその名宛人である相続人が亡くなった場合、その子が遺言書のとおり、代襲相続できるの?
遺産相続の基礎知識
身内が亡くなったが、誰が財産を引き継ぐの?
まず、亡くなった方(被相続人)が、遺言書を書いていた場合には、原則として、その遺言書の内容に従って、財産が承継されます。
もっとも、被相続人の配偶者や子ども、父母については、遺言により、相続財産を取得できない場合であっても、遺留分(いりゅうぶん)という権利を行使することにより、一定の財産を取得できる可能性があります(兄弟姉妹に遺留分はありません)。
遺言書がない場合には、民法の規定に従って相続人と相続分が決定されます。
- 配偶者(妻または夫)は常に相続人になります。
- 子どもは、配偶者とともに相続人になります。
- 父母は子どもがいないときに、相続人になります。
- 兄弟姉妹は、子どもも、父母もいないときに相続人になります。
相続分は、配偶者と子の場合は1:1、配偶者と父母の場合は2:1、配偶者と兄弟姉妹の場合は3:1です。
※子が複数いる場合には、子の相続分を人数で均等配分します。
例えば、配偶者がいて子2人の場合
配偶者2分の1、子4分の1、4分の1
1.につき、離婚した配偶者や内縁関係の夫や妻には相続されません。
2.につき、
ア)被相続人死亡時に胎児であった子どもも生まれてきた場合には相続人になります。
イ)婚姻外で生まれてきた子どもについては、認知されていれば相続人となります(但し相続分は実子の2分の1)。
被相続人が亡くなった後で、裁判所に認知を請求する手続もあります。
ウ)被相続人が亡くなったとき、既に被相続人の子どもが亡くなっていて、その子ども(=被相続人の孫)や孫(被相続人のひ孫)がいる場合には、その方が相続人になります(代襲相続)。
3.につき、被相続人が亡くなったとき、被相続人の父母はいないが、祖父母がいるときは、祖父母が、相続人となります。
4.につき、兄弟姉妹についても、代襲相続があり、甥や姪が相続人になることもあります。
なお、相続人が誰もいない場合には、利害関係人の請求によって、家庭裁判所において相続財産の管理手続が行われ、特別縁故者に対して相続財産の分与がなされる場合があります。
身内がなくなったが、相続財産としてどのようなものがあるか分からない。調査方法はあるの?
相続財産としては、不動産(土地、建物)、預貯金、現金、有価証券、動産(自動車、
宝石、骨董品他)があります。
多額の相続財産があることが明らかである場合には、相続税申告のため、相続人が税理士に依頼していることが多く、ある程度調査が進んでいるケースが多いものと思われます。
以下は、自ら調査しなければならない場合の調査方法です。
不動産
法務局で登記簿謄本を取得し、名義を確認してみて下さい。
被相続人名義の不動産が一覧になっている名寄帳(土地家屋課税台帳とも呼ばれます)を
不動産所在地の市町村役所の資産税課で取り寄せることができる場合もあり、その場合、
被相続人の所有不動産が分かります。
預貯金
通帳がある場合には、発行支店において残高証明書の発行・取引履歴の照会を依頼してみて下さい。通帳がない場合には、年金や給与の振込先の銀行に照会をかけるなど、被相続人の生活圏に存在する金融機関を一通りあたってみると預金の存在が分かる可能性があります
(その場合、被相続人の生前の状況から貸金庫の契約などをしている可能性があれば、併せて問い合わせてみるとよいでしょう)。
有価証券
自宅内を調査することによって、証券や証券会社からの郵便物から有価証券の存在が見つかる場合もありますが、そうでない場合、通帳の履歴、銀行から取り寄せた取引履歴から、分かる場合もあるでしょう。
被相続人宛の郵便物、預金通帳の履歴を調べることで、被相続人の財産状況についていろいろと分かることがありますので、ご確認下さい。
また、郵便物の中に請求書や催告書がある場合や被相続人の自宅に貸金業者に対する振込明細書や借用証等が発見された場合には、被相続人に借金が残っている可能性があります。
その場合は、貸金業者等に対し、いくらの残債務が残っているのかを照会し、プラスの財産と比較して、急ぎ相続放棄の手続をしたほうがよいかを検討して下さい(すぐに相続放棄をするかどうか判断できない場合、「相続放棄の期間の伸長」もご検討ください)。
亡くなった夫が、借金を負っていたが、支払わなければならないの?
借金も「相続財産」として、相続人(配偶者、子等)が引き継ぐことになりますが、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったとき(=原則として、被相続人が亡くなったことを知ったとき)から3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の手続をとれば、
借金を引き継がずにすむことができます。
ただし、被相続人名義の不動産の登記を自分名義にしたり、被相続人の預金を引き出して使った場合には、相続を承認してしまうことになりますので、相続放棄をすることはできません。
もっとも、相続放棄をしますと、プラスの資産についても相続することができなくなるので注意が必要です。
詳しくは、「相続放棄Q&A~相続放棄についてよくある質問」をごらんください。
※亡くなった方が、保証人になっていたときには、相続人は、保証債務も相続することになるので注意が必要です。
※相続放棄をしても、保険金の受取人に指定されていれば、保険金は受け取ることができます。
遺言の基礎知識
そもそも遺言はなぜするの?
遺言とは、遺言をしようとする者が、将来自分が死んだときに、自身が築き上げてきた大切な財産を有意義に活用してもらうために行う意思表示です。
法的に有効な遺言を作成することにより、相続人の意思にかかわらずに、遺言者が一番良いと考える方法での遺産の分割が可能となります。そのため、相続人間の不要な争いを回避することにもつながります。
遺言がない場合には、どのように相続がなされるのか
被相続人(亡くなった人)が生前に遺言を作成していない場合には、民法の規定に則って、
原則として、法定相続人がその法定相続分の相続を受けることになります。
そのため、相続人は被相続人の配偶者(内縁の妻を除く)と子、子がいない場合には被相続人の直系尊属、直系尊属もいない場合には被相続人の兄弟姉妹というように、法律で決められた人のみが遺産を相続することになり、その他の人は相続することができません。
法定相続人以外の人に遺産を与えたい場合や、法定相続分を超えて特定の人に遺産を分割したい場合には、被相続人本人が、生前に、その旨を記載した遺言を作成する必要があります。
遺言の具体的なメリットとデメリット
メリット
- 法定相続人に限らず、財産の形成に貢献してくれた人や、生前、特に面倒を見てくれた人などに、財産を相続させ、または遺贈させることができる
- 遺留分権者の権利を害さない限りにおいて、法定相続分にとらわれずに財産を分割することができる(ただし、相続人間の公平を考慮することは必要)
- 相続人間の公平を欠かない形での遺産分割の指定をすることにより、将来の遺産分割における紛争を予防する役割を果たす
- 不動産の登記や銀行等の手続を円滑に勧めることができる
デメリット
- 遺言の内容が不明確な場合や、法が要件とする方式に不備がある場合には無効となるため、有効・無効をめぐって新たな紛争が生じる可能性がある
(特に自筆証書遺言の場合)

遺言にすれば、なんでも実現可能?
結論からいえば、遺言として法的強制力が生じる事項は民法の規定によって制限されており、遺言に書いたからといって、何が何でも法的に実現可能となるわけではありません。
また、民法は遺言の種類・方式を極めて厳格に制限しており、これらの方式をみたさない遺言はそもそも何らの効力を持たない、無効なものとして取り扱うこととされています(法的効力は生じませんが、道義的には考慮すべきものとされます)。
遺言においてこのような取扱いがされているのはなぜでしょうか。
そもそも遺言は、遺言者が亡くなった後にその効力を発揮します。そのため、いざその遺言が本当に遺言者の意思によって作成されたものかどうかが争われたとき、つまり、その遺言が有効なものであるかどうかが問題となったときには、遺言者自身がすでになくなっているため、それを確かめる術がありません。そのため、我が国では、その遺言が遺言者本人の意思によるものであることを法が担保する方法により、その問題の解決を図っているのです。
つまり遺言は、遺言者本人によって、民法が定める厳格な方式に従って作成されてはじめて、本人の意思によって書かれた遺言として法的に認められ、遺言としての効力を持つことになるのです。
また、有効な遺言は相続人を拘束しますので、その内容についても法的に強制可能なものでなければなりません。そのため、遺言として効力が生じる事項についても、民法が制限を加えており、民法が挙げる事項以外のことを書いたとしても、それには遺言としての効力はないものとされているのです。
民法が定める遺言の方式と遺言事項
(遺言の内容として法的効力がある事項)
まず、民法は、遺言の種類として普通様式と特別様式を用意しています。
特別様式の遺言は、病気で重体に陥ったため、遺言者自身で遺言を作成することができない
場合や、在船者等で普通様式の遺言が利用できない場合などに利用されますが、そのような
特別な状況に置かれている人でなければ、普通様式の遺言を利用することになります。
普通方式の遺言には以下の3つがあります。
自筆証書遺言
規定条文 | 民法968条 |
|---|---|
遺言の方法 | 遺言者が遺言書の全文、日付(日付が特定できる記載でなければならない)、氏名を自署し、押印する。遺言書中の加除その他変更をする場合には、遺言者自身が、遺言書の余白等においてその場所を指示し、変更した旨を記載して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印をする。 ※改正法によって2019年1月13日以降は、財産目録については、手書きで作成する必要がなくなりました。パソコンで目録を作成したり、預金通帳のコピーを添付でもOKです(ただし、財産目録には署名押印が必要です) |
検認手続 | 必要 ※2020年7月10日からは、法務局における自筆証書遺言の保管制度を活用した場合には、家庭裁判所の検認手続が不要となります。 |
メリット | 紙と筆記用具があれば自分ひとりで書くことができる。特に費用はかからない。遺言の存在・内容を知られることなく作成することができる。 |
デメリット | 内容の不明確、民法が要求する方式の不備等により、遺言が無効となる場合がある。遺言者以外による遺言書の改ざん・破棄・隠匿や、紛失といったおそれがある(そもそも発見されずに遺産分割が行われてしまうおそれもあり)。必ず遺言者自身が自筆しなければならないため、自身で文字を書くことができない場合には利用できない。 |
公正証書遺言
規定条文 | 民法969条 |
|---|---|
遺言の方法 | 公証役場において、証人2人以上の立ち会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する。 |
検認手続 | 不要 |
メリット | 内容の不明確、方式の不備等で遺言が無効になるおそれがない。公証役場に遺言書の原本が保管されるため、内容の改ざん・破棄・隠匿等による心配はない。自筆する必要がないので、自力で文字を書くことができない人でも利用できる。 |
デメリット | 証人や公証人に遺言の内容を知られてしまう。作成に費用がかかる。 |
秘密証書遺言
規定条文 | 民法970条 |
|---|---|
遺言の方法 | 遺言者が、遺言書に署名押印をした上でこれを封じ、遺言書に押印したもの同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前で自己の遺言書である旨その他を申述し、公証人、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印して作成する。 |
検認手続 | 必要 |
メリット | 遺言書が遺言者本人のものであることを明確にすることができ、かつ、内容を秘密にすることができる。遺言書を自筆する必要がないので、第三者による代筆や、ワープロによっても遺言を作成することができる。 |
デメリット | 公証人は、遺言の内容を確認することができないので、内容が不明確であったり、方式に不備があったりした場合には、遺言が無効になる可能性がある。封紙上に自署等をする必要があるため、病気等で字が書けない場合には利用できない。 |
主に利用されるのは自筆証書と公正証書遺言です。自筆証書遺言は、自分の好きなときに自分ひとりで書くことができ、費用もかからないため、最も手軽な方法ともいえますが、それなりのリスクも存在します。また、法的に内容が不明確・曖昧と評価されれば遺言としての効力がなくなってしまいますので、書き方にも注意が必要です。
その点、費用はかかりますが、公正証書遺言では専門家である公証人が作成に関与しますので、無効となることはまずありません。また、公証人から様々なアドバイスを聞きながら遺言を作成することができますので、遺言者にとっても有意義な遺言を作成することができると思われます。
なお、話すことができない方でも、通訳を介することによって、公正証書遺言、秘密証書遺言ともに利用することができます。
次に、民法が定める、遺言として法的な効果が生じる事項(遺言事項)としては、以下のものがあります。
身分に関する事項 | (1)子の認知 (2)未成年後見人・後見監督人の指定 (3)財産管理のみの未成年後見人の指定 |
|---|---|
相続に関する事項 | (4)推定相続人の排除および排除の取消し (5)相続分の指定、相続分の指定の第三者への委託 (6)遺産分割の方法の指定、遺産分割の指定の第三者への委託 (7)遺産分割の禁止(5年間限り) (8)遺産分割における担保責任に関する別段の意思表示 (9)負担付遺贈の受遺者が放棄した場合についての指示 (10)負担付遺贈の目的の価値減少の場合についての指示 (11)遺留分減殺方法の定め |
相続以外の財産処分に関する事項 | (12)遺贈 (13)一般財団法人設立のための寄付行為 (14)信託の設定 (15)生命保険の死亡保険金の受取人の指定・変更 |
遺言執行に関する事項 | (16)遺言執行者の指定および指定の第三者への委託 |
解釈上、遺言でなし得るとされている事項 | (17)特別受益の払戻しの免除 (18)祭祀承継者の指定 (19)未成年者への無償贈与財産を親権者に管理させない意思表示と管理者の指定 |
これ以外の事項、例えば、「子ども達は、私の死後、母親を大切にすること」、「私が生前所有していた田んぼは決して手放さないこと」などを書いたとしても、それを相続人に法的に強制させることはできません。ただ、道義上尊重されることにはなるでしょう。
検認とは?
遺言をした人が死亡後に遺言書が出てきた場合には、すぐに開封せずに家庭裁判所に提出して、「検認」をうける必要があります。検認手続を経なければ、遺言の執行ができません。ただし、公正証書遺言の場合は、必要ありません。
家庭裁判所では、期日を定めて相続人を集め、開封し、遺言書の状態を調査し、検認調書を作成します。ただし、遺言書の検認はその遺言が有効かどうかを決めるものではありませんので、検認を受けなかったから無効になるというものではありません。
しかし、遺言書を提出しなかったり、勝手に開封したりすると、5万円以下の過料に処せられます。また、遺言書を提出しないだけでなく、隠したりすると相続できなくなってしまいますので注意して下さい。
検認手続を経た後、遺言執行者が指定されていれば、その者が遺言執行を行います。遺言執行者がいない場合には、相続人の協議で分割できればそれでもよいのですが、遺言執行者を家庭裁判所に申し立てて決めてもらい、遺言執行者が遺言執行を行うということもできます。
遺言は、遺言者の最終意思を尊重しようとする制度ですが、そのためには、遺言として書かれた遺言者の意思を第三者の偽造・変造・毀損から保護する必要があります。
きちんとした遺言書を作成するには、専門家のアドバイスを受けると安心です。
あやめ法律事務所では、遺言書の作成のアドバイスも行っております。
ご相談のご予約は022−779−5431までお気軽にどうぞ。
遺言書作成の費用のめやす(税抜)
| 定形的なもの | 10万円 |
|---|---|
| 非定形的なもの | 10万円に難易度に応じて加算いたします。 |
公正証書遺言の場合には、公証人費用の実費が別途かかります。
遺留分の基礎知識
遺言者は、遺言によって、相続財産を自由に相続人のみならず相続人以外の第三者に遺贈することができますが、例えば、遺言者が遺言で第三者に全財産を遺贈するとした場合、相続人としてはたまったものではありませんよね。そのため民法は、配偶者・子・直系尊属の相続人には「遺留分」を認め、遺言の内容にかかわらず、一定の財産を確保することができるようにしています。
遺留分を持っている推定相続人の遺留分を侵害して遺言が行われた場合には、遺留分を侵害された者は、遺留分を侵害する遺贈を受けた者に対して、遺留分を侵害した相続分に相当する金銭を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求権」と言います。
遺留分の侵害となるような遺言も当然に無効となるわけではなく、遺留分権利者が遺留分を侵害する遺贈や贈与を削ることの請求ができるということです。遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは、自由で、遺言のとおりでよいというのであれば、何もしなければよいだけす。
遺留分侵害されたかどうかは、遺留分の基礎となる財産(被相続人死亡時の財産+相続開始前1年以内に贈与した財産+遺留分を侵害することを双方が知っていた場合の贈与財産)に、遺留分権者の遺留分(相続人が、父母など直系尊属の場合は3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1)をかけて、各人の遺留分を計算し、それと遺言による遺留分権者の相続財産とを比較して、確認します。
遺留分侵害額請求は必ずしも訴訟によるわけではなく、侵害している相手方に意思表示を行えばよいのです。ただ、後日の証拠となるように「内容証明郵便」でするとよいでしょう。
侵害した者が遺留分を侵害した分を返還してくれればいいですが、応じてくれない場合は、通常の民事訴訟や遺産分割の審判を申し立てることになります。
遺留分侵害額請求は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年、あるいは相続開始から10年を経過したときは消滅してしまいますので注意が必要です。
遺言が見つかって、この遺言は遺留分を侵害しているのではないか、その場合には遺留分を主張したい、あるいは遺留分を主張されたがどのように対応したらよいか分からない、といったこともあるでしょう。そのようなときには、お気軽に、あやめ法律事務所(022-779-5431)まで、ご相談ください。
被相続人の預金引き出し
被相続人が亡くなると、預金口座は凍結され、相続人の一人が簡単におろすことはできなくなります(原則、払い出し書類に相続人全員の署名押印が必要です)。この点について、今回の相続法改正では、預金引き出しを従前より容易にしました。
今度の改正で具体的に何が変わるのでしょう?
(この改正点は、令和2年の7月1日の後に相続が発生した場合に適用されます)
詳しくはこちらをクリック
法律相談のご予約

お気軽にご相談ください。
お電話でのご予約はこちら
022-779-5431
相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで
メールでの受付は、24時間行っております(折り返しのご連絡は、基本的に上記受付時間となります)。
借金、相続、離婚、交通事故、不貞慰謝料の相談料は30分以内無料です。その他の事件は、30分あたり5500円です。
※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。
※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。
※取扱い地域
仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域
無料法律相談のご予約
コラム
- バーガー国ものがたり~3つのアイデア:自然権、社会契約、法の支配
- 他人と比べないこと(R3.11.15)
- 生きがいについて(R2.11.23)
- 所有権絶対の原則!(R2.4.6)
- 長男の妻の労苦は報われるのか?(R2.4.2)
- 配偶者居住権が新設されました(R2.4.1)
- パワハラをしないためには知識が必要です!(R2.3.25)
- こども六法(R1.9.24)
- 国民主権って何だろう?(R1.7.15)
- 裁判官はどのように判断しているのか?(R1.7.6)
- 自分の主観と相手の主観とはズレているもの(R1.6.30)
- 本当に怖いセクハラパワハラ問題(R1.6.22)
- 愛の本2 自分以外の人は全て他者(H31.2.10)
- 愛の本 他者との〈つながり〉を持て余すあなたへ(H31.2.3記)
- 自分の一番の味方は自分(H31.1.21)
- 友だち幻想3 人生の苦味・うま味(H30.9.9)
- 対人距離がわからない(H30.8.6)
- 正義とは他者に対する公正さ(H30.7.15)
- 人間関係に悩んだら、とりあえず「登場人物」を紙に書きだす(H30.6.12)
- 友だち幻想2 距離の感覚(H30.5.29)
- 友だち幻想 人と人のつなばりを考える①(H30.5.14)
- 主観的に大切なこと、客観的に重要なこと(H30.5.3)
- 自己開示の効用(H29.12.23)
- 人生は思うようにはならないもの(H29.9.21)
- 正義って何?~反転可能性テスト(H29.9.16)
- 悩んだら、とりあえず散歩(H29.6.25)
- 自分に価値があると思えるために2(H29.4.27)
- 自分に価値があると思えるために(H29.3.5)
- 3人のレンガ職人(H28.9.26)
- よく生きるために働くということ(H28.9.18)
- 弘前の桜(H27.5.8)
- 取引先破綻の商品引き上げについて
- ずっと運の悪い人はいませんよ。
- 第○回の調停を始めます! (H26.8.30)
- 複数のスポーク
(H26.8.14) - 嫉妬心とのつきあい方(H26.7.27)
- 本当は仲直りがしたいのに (H26.6.15)