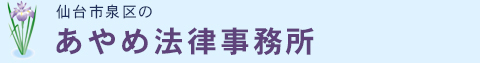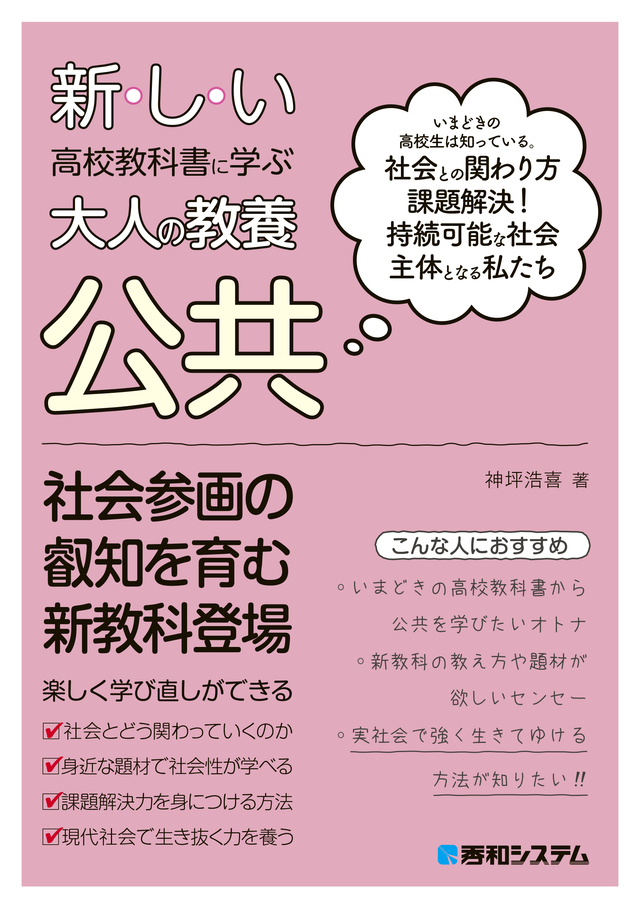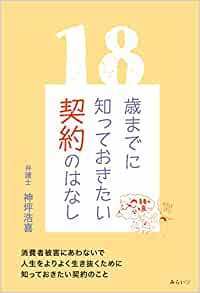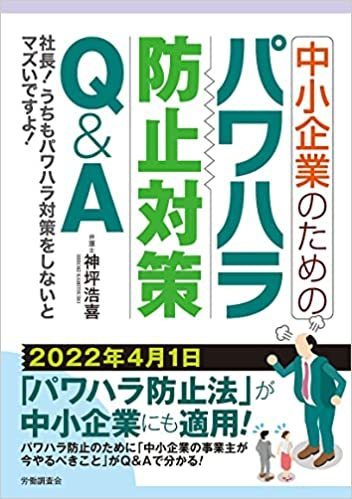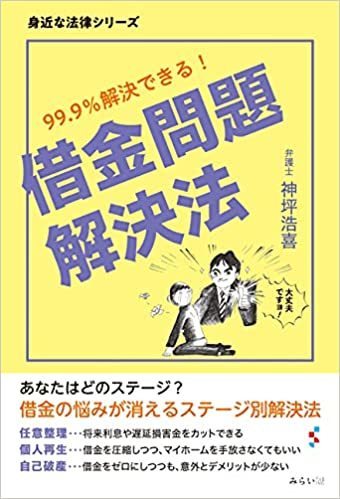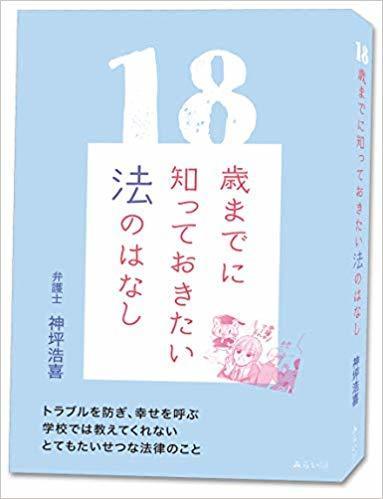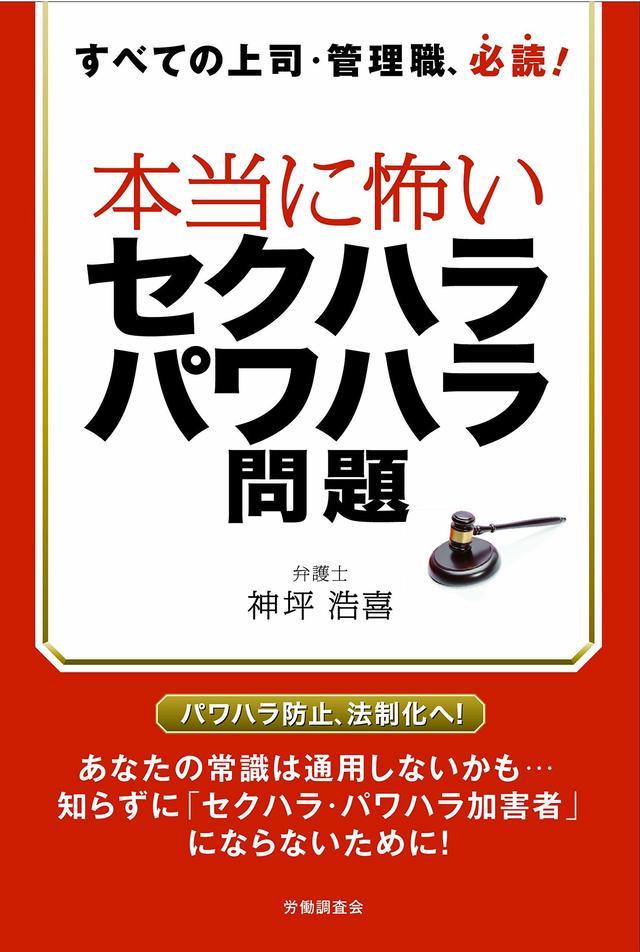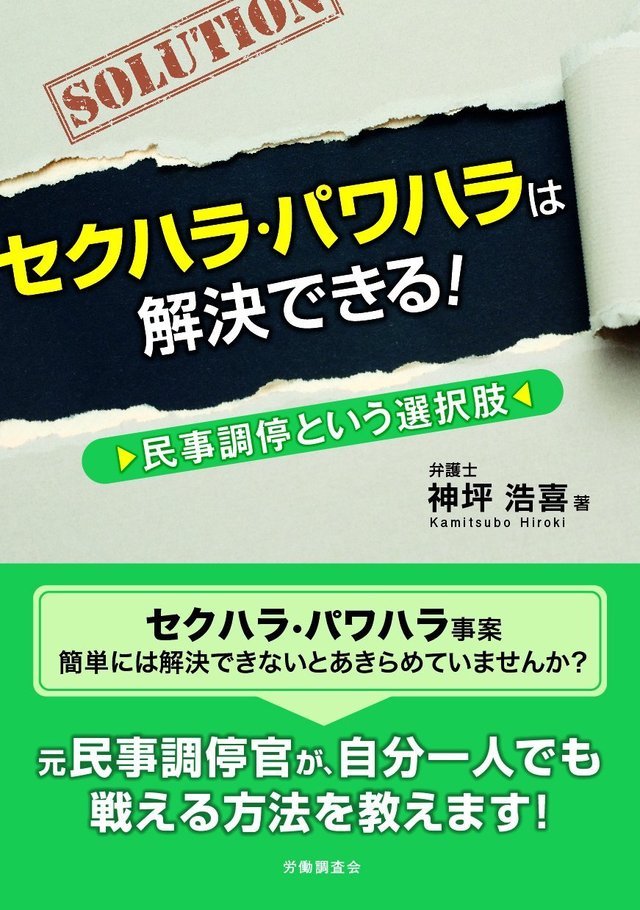宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
<お電話での相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後0時20分
午後1時20分から午後5時15分まで
メールでは24時間受付
「相続させる遺言」をした遺言者より先に、その名宛人
である相続人が亡くなった場合、その子が相続できるの?

Q:相続させる遺言をした遺言者より先に、名宛人である相続人が亡くなったとき、代襲相続は発生するのでしょうか?
例えば、祖父Aが遺言で、「父Bに甲の土地を相続させる」としていたところ、祖父が亡くなるより先に、父Bが亡くなった場合、その遺言によって、代襲相続人である私C(父Bの子、祖父Aの孫)が、土地甲を相続できるのでしょうか?
A:代襲相続は、原則として発生しません。
法定相続としては、被相続人の祖父が亡くなる前に、相続人の父が亡くなった場合、父の相続人の子(祖父から言えば孫)が、亡くなった父に代わって相続人になることができます。これを代襲相続と言います。
では、遺言書に書いたことも、代襲されるのでしょうか?
ところで、遺言に書く末尾の文言として、「○○を遺贈する」「○○を相続させる」というパターンがあります。
「遺贈」というのは、遺言で財産を他人に無償で与えることで、与える先は、相続人であることも 相続人でないこともあります。
他方で、「相続させる」は、相続人に対しての遺産分割方法の指定という意味合いとなり「相続させる」という文言が使えるのは、相続人に限られます。
相続人ではない人、例えば世話になった長男のお嫁さんに、財産をあげたい場合には、「相続させる」とは書けません。ですから「遺贈する」という言葉を使います。
財産を与える先が、相続人であれば「相続させる」遺言にしておきましょう。
それは「相続させる」が、「遺贈する」言葉の遺言より、有利だからです。例えば、「遺贈する」と遺言に書いた場合は、遺贈を受ける者は、所有権移転登記をするために他の相続人全員の印鑑、印鑑証明書が必要(ただし遺言執行者がいれば遺言執行者と共同でOK)になりますが、「相続させる」の場合には、相続されると名宛人となった相続人だけで、所有権移転登記申請をすることができます。相続開始時に、遺言に従って、所有権が指定された相続人に移転していることになっています。
財産を与える先が、相続人ならば、「○○を相続させる」と書いておけば無難です。
ところで、設問は「相続させる」遺言についてですが、遺贈の場合には、法律上、明確に、遺言は代襲されない、孫にはいかないと書かれています。
「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と規定があるのです(民法994条1項)。したがって、「○○を遺贈する」という遺言の場合には、その部分の遺言は無効であり、受遺者の子に受け継がれることはありません。
ところが「相続させる」の場合については、そもそも「相続させる遺言」について、条文がなく、最高裁平成3年4月19日判決で原則として遺産分割の方法が指定されたものとして、遺言の方法として明確に位置づけられたものです。
そして、相続させる遺言をした遺言者より先に、名宛人である相続人が亡くなったとき、代襲相続は発生するのか?といった問いについて、下級審では、肯定するものと否定するものとがありました。
しかし、最近(平成23年2月22日)の最高裁判決で、次のように述べて「原則として、代襲相続は発生しない」とされました。遺贈と同じですね。「遺言書に書かれた財産をあげる先は、宛名に書かれたその人限りというのが通常でしょう」という感覚で、孫にはいかないとされたのです。
「上記のような『相続させる』旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」
祖父が代々引き継いできたお店を長男と一緒にやっていて、長男に店を譲りたいと考えて、長男に店に関する不動産をあげるとしていたような事情で、孫もお店を引き継ぐつもりで一緒にお店を手伝っているような場合、祖父の意思を他の相続人もしっているような場合には、「特段の事情あり」として、孫への相続が認められるのかも知れませんが、原則は、代襲されないのです。
遺言書の「長男に土地を相続させる」という遺言に効力が生じない場合には、その土地の帰属は、相続人間で協議して、決めることになるでしょう。
ですから、長男が亡くなったときは、すぐに遺言書を新しく作成しなおすか、あらかじめ、自分より先に長男が亡くなることにも備えて「○○の不動産は長男に相続させる。長男が自分より先に亡くなったときは、孫に相続させる」といった遺言書を書いておく必要があります。
長男宛に「お店の不動産を相続させる」と遺言書を書いてさえおけば、もう大丈夫と安心される方もおられるかも知れませんが、このような落とし穴があるので、遺言書の作成には、注意が必要です。
法律相談のご予約

お気軽にご相談ください。
お電話でのご予約はこちら
022-779-5431
相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで
メールでの受付は、24時間行っております(折り返しのご連絡は、基本的に上記受付時間となります)。
借金、相続、離婚、交通事故、不貞慰謝料の相談料は30分以内無料です。その他の事件は、30分あたり5500円です。
※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。
※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。
※取扱い地域
仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域
無料法律相談のご予約
コラム
- バーガー国ものがたり~3つのアイデア:自然権、社会契約、法の支配
- 他人と比べないこと(R3.11.15)
- 生きがいについて(R2.11.23)
- 所有権絶対の原則!(R2.4.6)
- 長男の妻の労苦は報われるのか?(R2.4.2)
- 配偶者居住権が新設されました(R2.4.1)
- パワハラをしないためには知識が必要です!(R2.3.25)
- こども六法(R1.9.24)
- 国民主権って何だろう?(R1.7.15)
- 裁判官はどのように判断しているのか?(R1.7.6)
- 自分の主観と相手の主観とはズレているもの(R1.6.30)
- 本当に怖いセクハラパワハラ問題(R1.6.22)
- 愛の本2 自分以外の人は全て他者(H31.2.10)
- 愛の本 他者との〈つながり〉を持て余すあなたへ(H31.2.3記)
- 自分の一番の味方は自分(H31.1.21)
- 友だち幻想3 人生の苦味・うま味(H30.9.9)
- 対人距離がわからない(H30.8.6)
- 正義とは他者に対する公正さ(H30.7.15)
- 人間関係に悩んだら、とりあえず「登場人物」を紙に書きだす(H30.6.12)
- 友だち幻想2 距離の感覚(H30.5.29)
- 友だち幻想 人と人のつなばりを考える①(H30.5.14)
- 主観的に大切なこと、客観的に重要なこと(H30.5.3)
- 自己開示の効用(H29.12.23)
- 人生は思うようにはならないもの(H29.9.21)
- 正義って何?~反転可能性テスト(H29.9.16)
- 悩んだら、とりあえず散歩(H29.6.25)
- 自分に価値があると思えるために2(H29.4.27)
- 自分に価値があると思えるために(H29.3.5)
- 3人のレンガ職人(H28.9.26)
- よく生きるために働くということ(H28.9.18)
- 弘前の桜(H27.5.8)
- 取引先破綻の商品引き上げについて
- ずっと運の悪い人はいませんよ。
- 第○回の調停を始めます! (H26.8.30)
- 複数のスポーク
(H26.8.14) - 嫉妬心とのつきあい方(H26.7.27)
- 本当は仲直りがしたいのに (H26.6.15)