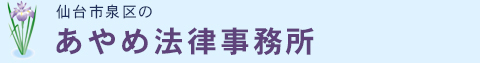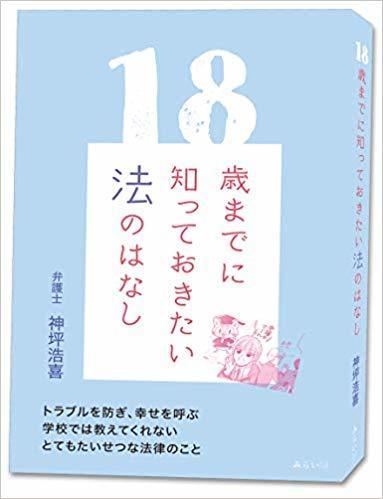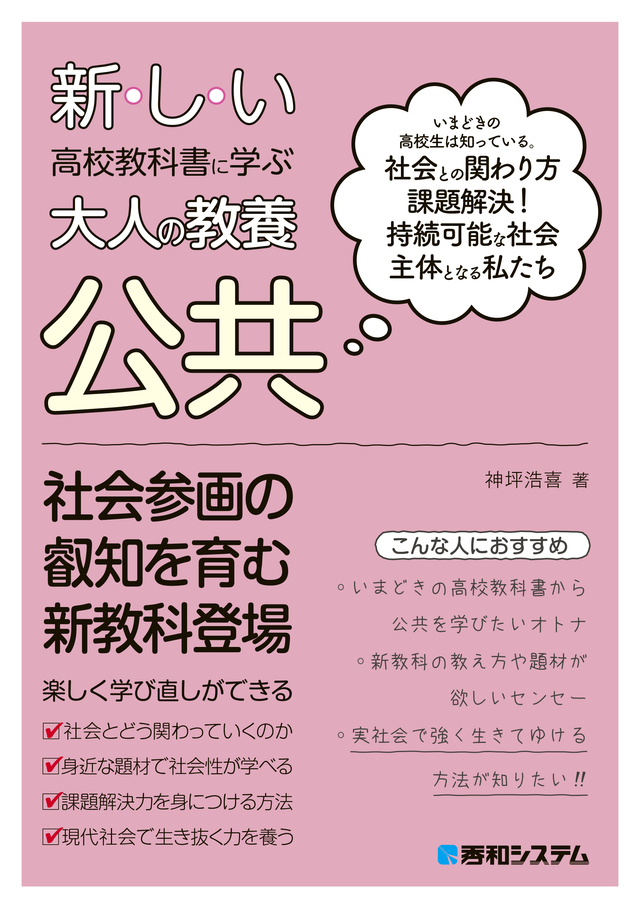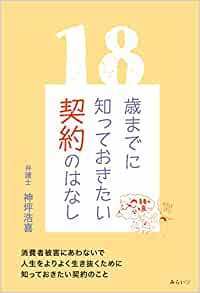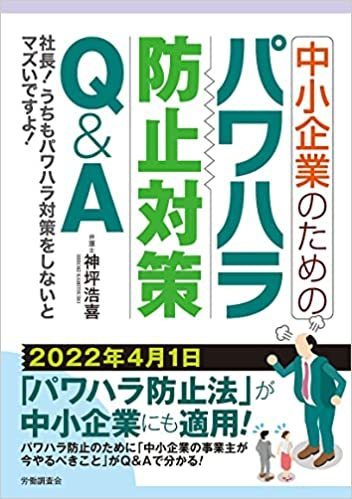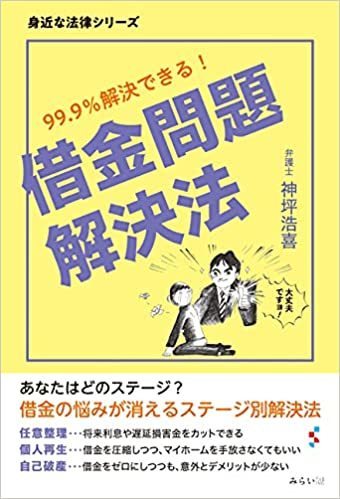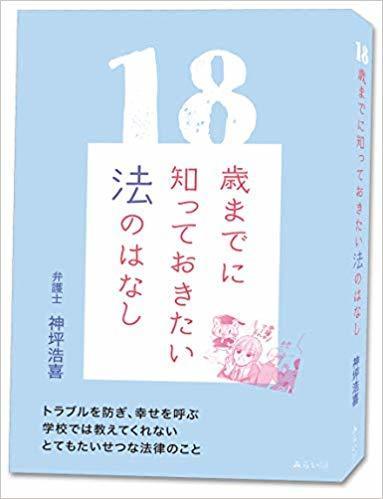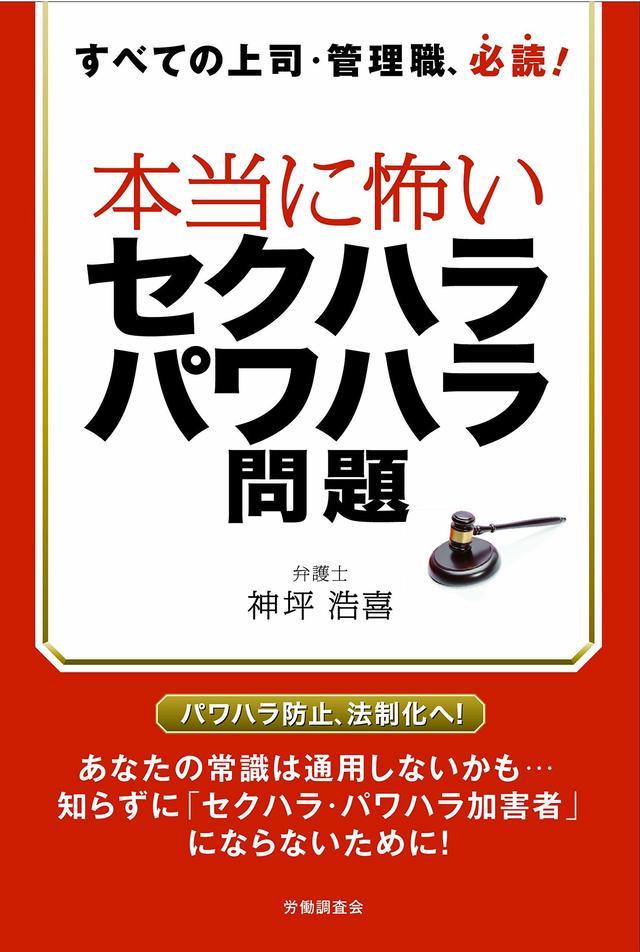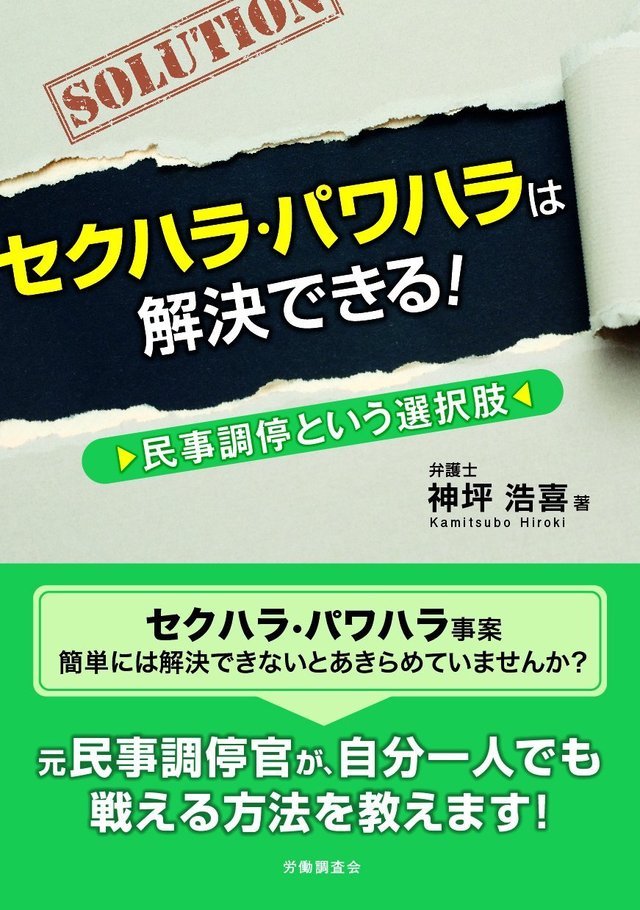宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
<お電話での相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後0時20分
午後1時20分から午後5時15分まで
メールでは24時間受付
民主主義と立憲主義のはなし
ダイジェスト版「立憲主義って何?」
「立憲主義」って何でしょう?
ひと言でいえば、権力の行使を憲法で縛る、コントロールすることです。
権力行使の主体は、国家です。つまり、立憲主義とは、国家権力を憲法で縛るシステムのことです。
日本国憲法は、「立憲主義」をとっています。
では、なぜ「立憲主義」がとられているのでしょう。
それは、一人ひとりが個人として、人として尊重されるという「個人の尊重」をまもるためです。個人の基本的人権が保障され、個人の権利自由が侵害されないために、です。
侵害するって、いったい誰が侵害するというのでしょう。
これは、国家、権力なのです。
ここはピンとこないかも知れませんね。
国家は、いろいろと国民のために、何かをしてくれるものではないの?
国、行政には、もっといろいろと「やってほしい」。
そのとおり、普段は、国、行政は、いろいろとやってくれるありがたい存在です。
でも、強い力、国民を強制できる力をもつ、時に怖い存在です。
税金を取られたくなくても、国が決めた税金は、強制的に取られてしまいますし、犯罪を犯したとされれば、刑務所に強制的に入れられますし、時に命までとられます。
権力には、強い力があるから、好き勝手に行使されてしまうとたまったものではないですよね。
憲法は、国民の権利自由を保障するために、国家に対して、「国民の○○の自由を侵害してはならない」という書き方を基本にしています。
「立憲主義」は、なぜ必要なのでしょう?
国家、権力によって、国家のためだとして、個人の基本的人権が侵害された歴史がありました。権力によって、一人ひとりのことよりも国家、団体、公が重視されて、個人の権利自由が侵害されてきた過去がありました。
特に、戦争というのは、究極的に、個人よりも国家を優先させ、個人を、一人ひとりの人ではなく、国家のための「道具」としてみなしがちです。
ここで、民主主義国家、国民から選挙で、選ばれた人たちなら、権力の行使も適正に行われて、暴走することはないのでは?と思われるかも知れません。
いやいや、民主主義国家であっても、憲法の縛りがなければ、間違った方向に行くこともありうるのです。逆に、国民から選ばれたんだと、謙虚さを忘れて、自分がやることは正しいのだと強気になってしまうかも知れない分、かえってやっかいです。
権力を持つものは、自らが誤りであることに気がつきづらいものです。正しいと思っている。自信があります。
正しいと思っているので、反対する人たちの声に耳を傾けることなく、「妨害する人たち」として排除したくなるでしょう。
多数者から選ばれた人たちからなるために、少数者の人のことがわからないこともあるのです。
そして、権力を行使するのは神様ではなく人なのですから、間違ってしまうこともあります。
間違っても、大切な基本的人権の保障を侵害しないように、国家が守るべき約束を定めて、約束を破れば、国民がコントロールできるようにしているのが「憲法」です。
つまり、 国家に権力を与えた国民が、権力行使を適正に行われるようにするため、国家をコントロールためのものが「憲法」なのです。
国家は、憲法に違反するような権力行使、すなわち個人の基本的人権を侵害することはできないという縛りをうけています。
逆にいえば、国民は、「憲法」を持っているのだから、国家が権力を濫用している場合、濫用しそうな場合に、しっかり国家を「憲法」をもとに、コントロールできるし、しなければならない、ということになるのですね。
「立憲主義」というのは、個人を尊重するために、一人ひとりを人として大切にするための、よくできたシステムだなあと思います。
(以下、本編です)
第1 民主主義のはなし
こんにちは。弁護士の神坪浩喜です。
民主主義と立憲主義の話をします。
「民主主義」「立憲主義」、そんな言葉を聞くだけで、分からない、難しそう、堅苦しい勘弁して、なんて思ってしまう人も多いかも知れないね。
でもこの国に暮らす上で、とても大切なことだから、知っておこう。
ところで、法律には、どんなものがあるか知っている?
キミも人の物を盗んだら、警察に捕まって、裁判にかけられて処罰される、刑務所に行くというのは知っているよね。
これは、国の法律で「人の物を盗んだら、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められているからなんだ。刑法のことだね。
刑法は、いろいろな犯罪と刑罰を定めている法律だ。人を怪我させたり、人を殺したりすると、刑務所に行くことになる、ときめている。
どうして、こんなきまりがあるのだろう。もし、刑法がないとどうなるだろう。
人を怪我させたり、人の物を盗んだりしても刑務所に行かなくてもよい、処罰されないとしたら、どうなるだろう?
そんな法律がなくても、自分は人を怪我させたり、盗んだりはしないよ。と思うかも知れないね。
うん、確かに、キミのように、人として、してはいいこといけないことが分かって、悪いことをしない人ばかりなら、刑法はいらないかも知れない。
でも、世の中にはいろいろな人がある。残念ながら、わがままで自分さえよければいい、他人のことを考えない悪い人も中にはいる。もし、刑法がなかったら・・・
うん、今よりもっと人の物を盗んでしまう、人が増えるかも知れないね。別に、人の物を盗んでも警察に捕まらないんだし、盗っちゃえ、なんて安易に盗ってしまうかも知れないね。盗まれた人が困るからと思うのではなくて、盗むと警察に捕まるから、自分は盗まないという人も結構いると思う。
自分の物、特に大切な物が、他人が勝手に持っていくのって嫌だよね。人が盗るなら、じゃあ自分も誰かから、物を盗ってしまおうなんて考えるようになるかも知れない。そうすると、そこでは盗ったり、盗られたりという世界になって、結局力の強い悪い奴がたくさん物を盗ったりして、無茶苦茶な世界になりそうだよね。それは、困る。安心して暮らせない。
そこで、刑法は、みんなが安心して暮らせるようにと、「特に人に迷惑をかけてしまうことをした人は、これこれの処罰を受ける」例えば「人の物を盗んだ者は、懲役10以下か50万円以下の罰金に処する」と刑法は定めた。
こういった法律があって、実際に、この法律に違反した人、人の物を盗った人が警察に捕まり処罰されることで、多くの人は、「人の物を盗ると警察に捕まるし、盗らないようにしよう。」と、人の物が欲しくなっても、盗ったりしないで、自分の行動をコントロールするんだね。これで、人の物を盗る人は、少なくなるでしょう。多くの人は、警察に逮捕され、刑務所に行くなんて、嫌だからね。
法律というのは、人の自由を制限しているといえる。人の物を勝手に盗りたい人にとっては「盗む自由」を制限されているとも言える。これは、盗まれる人のこと、物を持っている人の所有権(この物は私のものという権利)を保護しようと考えているからなんだ。自由があるといっても、人に迷惑をかけていいわけではない。人に迷惑をかける自由は保護されない。制限される。
法律は、人同士の自由と自由とがぶつかり合ったとき、調整をしているものといえる。
僕は、大きな声で歌を歌いたいんだ、大音響でエレキギターを弾きたいんだ、といって、みんなが寝静まった真夜中の住宅街で、大声で歌ったり、大音響でエレキギターを弾いちゃいけないよね。寝ている人の迷惑になる。そんなのダメだよと法律は定めている。
法律は、人と人との自由や権利を調整して、社会秩序をたもっているんだね。お互いに安全に、快適に暮らせるようにしている。
では、そんな法律は、どうやって作られるのだろう?どのように作られるのがいいのだろう?
特定の人、例えば王様や将軍が法律を決めるのってどうだろう?
昔は、王様や将軍といった特定の人が、法律を作っていた時代があったんだ。
昔、こんな感じの法律があったんだよ。
・キリスト教を信じてはならない。信じた者は処罰する
・動物(特に犬)を虐めてはならない。虐めた者は死刑とする。
・王様の政治を批判してはならない。批判した者は処罰する。
どう思う、こんな法律?
王様や将軍といった特定の人がものごと、法律を決めるのは問題があるというのは、多分キミ達にも感覚的に分かると思う。
どうして法律を特定の人が決めるといけないのだろう?
その王様が、自分の贅沢だけを考える悪い王様だったら、自分が贅沢したいので、税金をたくさんとるという法律を作るかも知れない。また、わがままな王様なら、国民から自分がやっていることを批判されたら嫌だということで、国の政治を批判する人をかたっぱしから刑務所に入れてしまえ!なんていう法律をつくってしまうかも知れない。
その王様が、結構いい人で、名君で、国民のためを思って法律を作ろうとしたらどうだろう。
例えば孔子(論語を書いた昔の中国の思想家)のような立派な人が、王様になって国を治めればいいのだろうか?
でも、いくら立派な王様であっても、王様が、国民それぞれがどんなことを考えているのか、何を望んでいるかはよく分からないだろう。王様が、国民のためによかれと思ってやったことでも、実際には国民にとって迷惑なこともあるだろう。国民にとっては余計なお世話というものもあるだろう。ピントがずれた政治を行ってしまうかもしれない。
それに、王様がいい人か悪い人かどうかで変わってしまうのって、人次第ということで、怖いよね。どんな王様になるかで、国民の生活も変わってきてしまう。そしてどんな王様になるかは、運命次第。歴史を勉強してくると分かるけど、その時の王様や将軍の考え方や好みなんかで、180度政治が変わってくることもある。
では、国のきまりは、王様とか特定の人が決めるのではなくて、どのようにして決めるのがいいのだろうか?
ところで、キミ達が、クラスで、何かを決める時って、みんなどうしている?例えば、文化祭のクラスの出し物ってどうやって決めている?
クラスの誰か、例えば学級委員とかが、適当に決めている?そんなことはないよね。みんなで話し合って決めていると思う。みんなでいろいろと意見を出して、ある人の意見がみんないいと思えばそれに決まる。
もし、みんないろいろと話し合っても、意見が分かれることがあれば、どうやって決めている?
じゃんけん?くじ引き?それもあるかも知れない。
でも、きっと手をあげてもらったりして、投票してもらったりして、数が多い方に決めることが多いよね。黒板に「正」の字を書いたりして。
つまり多数決で決める。それが、話し合ったことが生かされると思うから。いろいろ話し合った後に、くじ引きで決めるなんて、話し合った意味がないよね。
話し合いによって、いろいろな意見がでて、みんなの多くが、それがいいというのになるのが、納得がいくだろう。たいてい、みんなにとってそれがいい決まりになることが多いだろう。
では、どうして、キミ達は、みんなで話し合って決めているのかな?
それは、自分たちのことだから。自分たちに関することは、自分たち以外の誰かに決められたくないから。自分がそのグループにいる以上、自分の意見もいえるようにしたいから・・・だろう。
自分たちが従わなければならないルールならば、自分の意見も聞いてよと当然思うだろう。自分が知らないところで、勝手に決められたくないだろう。押しつけられたくないだろう。
勝手に決められたルールなんて、とルールを守る気にならないかも知れないね。
そして、みんなそんな風に思っていたら、決めたルールを守らない人が多くなって、ルールが骨抜きになってしまうだろう。
誰だって、自分の全く手の届かないところで決められたルールを押しつけられるのって嫌だよね。納得いかないよね。
1組のクラスの出し物を2組が決めるなんておかしいよね。
「自分たちのことは、自分たちで決める。」
ルールをつくる人たちとルールを守る人が一致していることが大切なんだ。
これを難しい言葉でいうと「自己統治(じことうち)」なんていう。
そして、自分たちで決めたルールならば、そのルールを大切にして、守ろうという気になるだろう。
それに、ある人が考えるより、みんなで意見を出し合って、話し合っていった方が、普通は、みんなにとっていいきまりになることも多いだろう。
キミが思いつかないことを別の友達が発言することもあるだろう。友達の発言を聞いていて、キミがいい案を思いつくこともあるだろう。
だから、みんなで意見を出し合いながら、話し合って決めた方がいいんだね。
いくら王様が頭のいい人であったとしても、みんなで力をあわせて考えたことには、及ばないことがほとんどだろう。
国のあり方、法律も同じこと。
①自分たちのルールは、ルールに従う自分たちで決めるべきということ
②みんなで意見を出し合いながら話し合った方が、いいルールができやすいこと
③自分たちがきめたルールだからこそ、そのルールを尊重し、守ろうとすること
だから、「みんなのことは、みんなが話し合って決める」ことにしたんだ。
これを、「民主主義」という。そして、世界の多くの国では、この「民主主義」の考え方を基本にして、国の政治のあり方を決めている。
それは、民主主義が、集団の中のものごとの決め方として、現在考え得る一番よい決め方として、受けとめられているからなんだ。
そして、国の政治以外でも、キミ達の普段の生活の中ででも、クラスとかの人の集まりに入っている以上、この民主主義がベースになっていると思う。
でも、国でも、身近な集まりでも、「民主主義」、みんながよく話し合って、ものごとを決めることが、本当に実践されているかどうかは、いろいろあって、「形だけの民主主義」ということが結構多かったりするんだ。
例えば、話し合いもせずに、他の意見もろくにきかずに、すぐに多数決で決めてしまうとかいうのは、「民主主義」を実践しているとは言えないだろう。判断のもとになる必要な情報を共有しないままで、決めてしまうというのも、やはり「民主主義」になっていない。
「形だけの民主主義」ではなく、「本当の民主主義」を実践するためには、単に多数決で決めさえすればいいという訳ではなくて、必要な情報を共有し、一人一人が意見を言える機会があって、みんなでよく話し合いをするという、みんなが努力する必要があるんだね。
ちょっと、今度のクラス会、私達は「本当の民主主義」でやっているかな?と、そんな目で見てごらん
第2 民主主義のはなし2-安易に多数決で決めないこと-
さて前回は、集団がある以上、個人と個人の自由を調整するために、みんなが安心して便利に暮らせるようにルール、法律がきめられる必要があることをお話しました。
そして、そのルールや法律は、王様といった特定の人が決めるのではなくて、みんなで話し合って決めるのがいいこと、そのような決め方を「民主主義」ということをお話しました。
もともと、ルールや法律を決めたのって、何のためだった?
王様が、好きなように国を動かすため?自分が贅沢をするため?
違うよね。
確かに昔は、国や王様や特定の集団のために、法律を決めて、国の政治を批判する国民を処罰したり、税金をしぼりとったりということもあった。
でも今は、そんな考え方は否定される。
では、何のためにルールや法律はあるのだろうか?
それは、一人ひとりの幸せの追求が目的となっている。
人が集まったときに、必ず起こってくる自由と自由の衝突の調整をはかって、一人ひとりが安全に快適に暮らせるようにしくことを目的にしているんだ。
国や特定の団体のためではなく、あくまで、個人の幸せが念頭にある。実は、このことが忘れがちになってしまうのだけれど、憲法は、そのことをはっきり規定している。
僕は、ここで大声で歌いたいんだ!と思っていても、仮にそこが図書館だったら、実際にそんなことをしたら、静かに本を読んでいる人たちにとってはえらい迷惑だよね。図書館で歌うことは禁止されている。
「図書館では、静かにすること」というきまりは、図書館は、本を読む場所なんだから、図書館で静かに本を読む人の利益を守っている。歌を歌うような場所ではないから、歌を歌う自由はそこでは保護されない。制限される。
キミ達は、タバコは吸ってはいないと思うけど(吸ってはいけないよ!)、大人では、タバコが好きな人とタバコの煙が嫌いな人が別れている。
タバコの好きな人は、吸いたいときに一服したい。でも、そこにタバコの煙が嫌いな人がいたら、吸ってもらいたくない。煙がきたら、露骨に嫌な顔をしたり、手で煙を払ったりする人もいるだろう。
場所によっては、ここは禁煙ですとか、タバコはこの場所で吸ってくださいと喫煙室が設けられていたりするよね。ハンバーガーショップやファミレスでも、喫煙できる場所と、禁煙の場所とかが別れていると思う。
吸いたい人とタバコの煙が嫌な人との自由が、ここでは禁煙とか、ここでタバコが吸えるのは、この部屋だけというようなきまりで、調整されているんだね。
こんなことから、ルールは必要になってくるのだけれども、それはあくまで、吸いたい人個人の自由と煙が嫌な人個人の調整のためなんだ。
では、民主主義の決め方ってどういうことなんだろう?個人の幸せを意識した決め方ってどうすればいいのだろう?
キミは「民主主義=多数決」って思っているかも知れないね。
でも、多数決で決めさえすれば、民主主義といえるのかな?
個人の幸せにとって多数決にさえしておけば、それがよい決め方といえるのかな?
ある会社で、喫煙グループの人達(タバコを自由に吸いたい!)と嫌煙グループの人達(タバコの煙が大嫌いだ)とに別れました。嫌煙グループが、煙が嫌いだから、社内全面禁煙という社内規則を作ろうと言い出し、両グループが話し合うことにした。
ここで、仮に喫煙グループが多数で、俺たちが多数なんだから、煙ぐらいがまんしてよ、というような感じでいきなり多数決で、「これまでどおり自由にタバコを吸ってもよい。」と決めるのはどうかな?
逆に、嫌煙グループが多数をしめていて、「これから、社内、全面禁煙です!タバコを社内で吸ったら罰金10万円!」なんて、数に任せて決めてしまったらどうかな?
民主主義のベースには確かに多数決があるけれど、いきなり多数決、安易に多数決というのは本当の民主主義になっていない。集団に所属する一人ひとりを大切にする決め方ではない。
前回の授業で、物事の決め方について、王様とか特定の人が決めるのではなくて、どうして民主主義がいいのか3つ理由をいいました。憶えているかな?
大切なことなので繰り返すよ。
① 自分たちのルールは、ルールに従う自分たちで決めるべきということ
②みんなで意見を出し合いながら話し合った方が、いいルールができやすいこと
③ 自分たちがきめたルールだからこそ、そのルールを尊重し、守ろうとすること
だったね。
もし、民主主義って単に多数決で決めればいいんでしょ、という感じで、いきなり多数決で決めたりするということは、少数派の人たちの存在を無視して「みんなで話し合って決める」いうことにはならないし、みんなで知恵をしぼって話し合えば、本当は多数派にとっても少数派にとってもいい案があるかもしれないのに、でてこない。
そして、少数派にとっては、多数派に無理に押しつけられた感じがして、「そんなルールなんて、守ってなんかやるものか。」なんてグレて決められたルールを無視したりするかも知れない。
そして、そんな決め方をしていると、そこには人と人との間に信頼関係はなくなって、ギスギスしたような関係になって、結局、みんなにとって住みにくい居心地が悪い集団になってしまう。
多数派が少数派を縛る、考えを押しつけるというような感じになってしまうかも知れない。
それって、王様がルールを決めるのと結局同じことだよね。たいして変わらない。
王様が縛るのではなくて、王様に代わって多数派が少数派を縛る。
「安易に多数決」では、少数派にとってみれば、「自分たちのことを自分たちが決める」こと、自己統治になっていないことになる。だって、自分たちの意見は、全然反映されないのだから。
それって、全然民主主義じゃないよね。一人ひとりが幸せになるようにルールを決めていることにはならないよね。
本当の民主主義といえるためには、よく話し合うということ、特に多数派の人達は少数派の意見に耳を傾けるという態度が大切になってくるんだ。
多数派の人達は、少数派の人達のことがよく分からないで、ついつい少数派の人達の意見を「わがままだ」「ひとりよがりだ」なんて考えてしまって、よく意見も聞かずに押しつけてしまいがちになるからね。
安易な多数決は、決して本当の民主主義ではないんだ。
第3 憲法は、国家を縛る、コントロールする-立憲主義のはなし1-
前回まで「民主主義のはなし」をお伝えしてきました。一人の人や特定の団体が権力を握って、物事を決めるのではなくて、みんなでよく話し合って決めた方がいいということだったね。
何のためにいいのか、それは個人の幸せにとっていいという意味だ。
ところで、権力って何だろう?権力って何のためにあるのだろう?
これは、ルールやきまり、法律が何のためにあるのかとつながっている。
ルールやきまり、法律は、何のためにあったのかな?例えば、前に話した刑法で、人の物を盗んだら懲役10年以下の刑に処するという規定は何のためにあったのでしょうか?
一人一人の安全を守り、安心してくらせるようにということだったね。
個人の幸せにつながることだね。
ルールやきまり、法律を強制的に守らせる力、それが「権力」ということになる。人の物を盗まないように、盗んだ人を裁判にかけて、法律に規定した処罰をあたえる。
盗んだ本人が、「そんなの嫌だ!刑務所なんか行きたくない!」と叫んでも、権力は、無理矢理逮捕し、裁判にかけ、刑務所に入れたりする。
他にも、自分は、税金を払いたくないと思っていても、法律上税金を払う義務がある場合には、法律の定めに従って、権力は、税金を強制的にとっていく。
そういった強制的にする力があるからこそ、一人ひとりの安全を守ったり、必要な道路や学校や病院をつくったりすることができるわけです。
もし、強制力がなければ、法律には「人の物を盗むのはいけない」と書いていても、盗んだ人を処罰することはできなくて、やはり盗むことが多い世界になるでしょう。
頑張って働いてお金をためて、欲しい物をようやく買ったのに、それが盗まれるなんて嫌だよね。がっくりするよね。人は弱いものだから、じゃあ別の人の物を盗ってやろうか、自分も盗られたんだしとそんな風に思うかもしれない。
もし、税金が強制的にとれなかったら、多くの人は、できれば自分の税金はあまり払いたくないと思うだろうから、必要な税収が確保できず、学校や病院、道路といった公共の施設をつくる費用や警察官や消防士、役所で働く人々(公務員)の給料も払えなくなって、学校や病院、必要な道路もつくれず、安全が確保できなかったり、大変不便な生活を強いられることになるだろう。
だから、国家に対して、権力が与えられている。国家は権力を持っている。時に、強制的に国民に何かをさせたり、禁止したりする力があるんだ。国家が、国民を強制的に従わせる力を「公権力」という。
とても強い、そして特別な力が国家にはあるんだね。
社会の秩序を確保すること、他の人を害することや迷惑になることをやめさせること、国が国民に対して必要なサービスを実施するために必要なお金を確保するために税金をとること、それは必要で、とても大切なことなんだ。
でも、公権力の使い方が間違っていたり、度が過ぎていたらどうだろう。
権力を実際につかうのは、神様ではなくて、ロボットでもなくて、個々の生身の人間だ。総理大臣も、国会議員も、警察官も、消防士さんも、裁判官も、税務署の職員さんも人間だね。
時に間違ったり、度が過ぎたりしてしまうことってあるかもしれない。人間なのだから、どうしても間違うことはある。完璧な人間なんていないし、そしてその人自身、社会生活を送り、感情を持つ人だから、どうしても間違ってしまうことはある。
強力な力を持つ人が、間違っていたり、度が過ぎていたら、どんなことになるだろう。
強い力だから、間違ったりすると、とても怖いことになる。
警察が、きちんと犯罪を犯した人を捕まえてくれるから、国民は安心して暮らせる。
でも、警察官が間違って逮捕して、検察官も間違って起訴して(裁判にかけて)、裁判官も間違って有罪判決をかけば、その人は、本当は何も悪いことはしていないのに、強制的に刑務所に入れられることもあるんだ。怖いことですが、実際に、これまでそんなことが、あったんだよ(これをえん罪といいます)。
そして権力には、その強大な力とともに、加え独特な性質があると思う。
まず、権力をもつ人は、自分のやっていることをあれこれ批判されるのは、苦手だ。自分のやっていることは「正義のため」で間違いはないと思いがちになる。
できれば、批判されたくない。国民には、自分のやっていることに素直に従順に従って欲しいと考える傾向にある。そして、ときには批判する人を排除したくなってしまう。
「国の政治を批判してはならない、批判した者は処罰する。」
こんな法律ってどう思う?おかしいよね。
きっと、冷静なときには多くの人がおかしいと思うだろう。でも、実際、過去にはこれと同じような法律があったんだ。ナチスドイツ・ヒトラーもそうだし、かつて戦争につきすすんだ日本でもそんな時代があったんだ。今現在でも世界には、同じような法律があり、国民が、国の政治を自由に批判することができない国もある。
権力が暴走してしまって、独裁政治になっている国では、言論の自由が否定されます。
そして権力は、大きくなろう、強くなろうという性質がある。国民を支配・コントールする力をもっとつけようという傾向がある。織田信長もチンギス・ハンも領土を拡大しようとした。強くなろうとした。国内では権力者に都合のいい法律をつくって、国民を統制しようとしがちだ。
また権力は、一定の思想や道徳と結びつき、それを国民に強制する傾向がある。そして、異質の考えや少数派の思想を排除しがちになる。権力にとって、異質の考え方の人がいると統治しにくくなるから、みんな同じ考え方の方が望ましいんだ。
それから、人が権力の場に長くとどまっていると、権力者自身の権力保持や拡大に向かって、国民個人の権利自由をないがしろになりがちだ。そして、国あっての個人なんだ、安全が守られるには個人は我慢しなければならないとかといって、国(権力を持つ者)や公を強調し、個人は犠牲になることをいいがちになる。
そして、権力は、間違ったとしても、間違いを認めません。認めたがりません。何か間違ったとき行き過ぎたときに、それを認め、反省して、自分の力で修正するということは、なかなか難しいことなんだ。別の第三者からのチェックはどうしても必要だ。
キミ達が学校でならった権力分立、三権分立は、権力を立法権、行政権、司法権と分散させて、相互に抑制と均衡、チェックアンドバランスを図ることで、権力が暴走して、個人の権利自由を侵害しないようにした仕組みなんだ。
歴史を眺めてみて、そして弁護士になってからの先生の刑事弁護等の体験からすると、権力にはどうしてもそのような傾向、性質が本来的にあるような気がする。
国家(=権力)は、一人ひとりの国民にとって、大切なもの、必要なものだけど、歴史から導かれる本来的な性質から、時に暴走し、間違いを起こし、そしてそうなってしまうと強大な力があるがために取り返しのつかない痛みを国民にもたらすことになる。
そしてかつて、国家(=権力)は暴走していまい、権力にとって気に入らない人を排除し、ひいては戦争につきすすみ、多くの人が大切な命、自由、財産を失うことになった。
人々は、二度とこんな悲しい目にあいたくないと思った。
二度とこんなことにならないようにしたいと思った。
そんなことにならないように、憲法を定め、国家(=権力)に縛り(しばり)をかけています。
権力が、暴走して、国民の権利自由を踏みにじることがないよう権力を分解し、国民がコントールできる仕組みをつくった。
憲法は、「国家(=権力)を縛るもの」
おそらくキミにとっては、初めて聞く言葉だと思う。
あれ?憲法って、法律で一番えらくて、国民が守るべきこと、道徳みたいな、何か大雑把なことが書かれているんじゃないの?
そう思っていなかったかな?いやいや、実は私自身、大学で憲法を学ぶ前は、そう思っていたんだ。それまで、日本国憲法の三原則は何?の穴埋め問題や、三権分立がどうのこうのとはか知っていましたが・・・
でも、憲法は、国民を縛ったり、ある行動を要求したりするのではなく、国家(=権力)を縛るものということが、実は憲法を理解する上での大切なポイントなんだよ!
時に、間違え、行き過ぎてしまう国家(=権力)におまかせにするのではなく、放っておくのではなく、権力に縛りをかけること、国民がコントロールできるようにしておくことが、憲法の本質なんだ。
私は、憲法は、国民の権利自由を確保するために、国家(=権力)を縛る、制限する、コントールするものだということをはじめて知って、「え?そうなの?」と驚きました。
憲法って、国に国民の大切な自由や権利を守るよう、国家に向けられたもの。国家に守らせようとするものなのか!と。
そして、この憲法の意味を知って、日本国憲法を眺めてみると、憲法というのは、権力の怖さ、個人の尊厳を踏みにじってしまった過去の失敗に、ほとほと懲りまくり、深く学び、それを理性でくい止めようとする世界や日本の人々の「苦心」や「決意」が見えてきて、感動した。
この憲法で国家を縛るという考え方を「立憲主義」(りっけんしゅぎ)という。
ちょっと堅苦しそうなとっつきにくそうな言葉だけど、民主主義と並んでとても大切な考え方なんだ。
では立憲主義は、前に話した民主主義とどのような関係にたつのだろうか?
憲法の条文で立憲主義の考え方はどのように反映されているだろうか?
第4 民主主義と立憲主義-多数決できめていいこと、いけないこと
前に、民主主義のはなしで、物事のきめかたとしては、みんなのことは、みんなでよく話し合って決める。意見が分かれたら、最後は多数決だけど、安易に多数決で決めないことも大切だということだった。
それでは、どんなことでも、みんなで多数決で決めてよいのかな?
まず、クラスの中でのことを考えてみよう。次の問いについて考えてみてごらん。
Q:次にあげることは、クラスみんなで多数決によって決めてよいことか、決めるべきではないことか考えてみましょう。
※多数決(たすうけつ)
会議などで、賛成者の多い方の意見によって物事を決めること
1 文化祭でのクラスの出し物
2 クラスの生徒一人ひとりの所属するクラブ活動
3 教室の掃除当番の決め方
① 文化祭のクラスの出し物で、「ブレーメンの音楽隊」の劇をすることになった。そこで、ロバの役をA君にしようと多くのクラスメイトが言い出した。A君は、「絶対嫌だ!」といっている。多数決でA君に決めてしまってよいのだろうか?
② 教室の掃除当番を、女子だけで交替にやってもらうという意見が出た。多数決で女子だけで交替にやってもらうということに決めてよいのだろうか?
さて、どうだろう?これを多数決で決めるのはちょっとまずいんじゃないの?というのもあったと思う。どうしてそう思うのか、言葉で説明してみよう。
解答は
多数決によって決めていいものは、1と3
多数決では決めるべきではないものと 2と①、②となる。
「1 文化祭でのクラスの出し物」と「3 教室の掃除当番の決め方」は、クラス全体に関すること、クラスに属する生徒全員に関することだから、みんなで、多数決で決めてよいことがらになる。
きまりをつくる人達ときまりに従う人達とが一致しているよね。
では、1組のクラスの出し物を2組で多数決で決めるのはどうかな?
これは当然、決めるべきではないことだよね。
1組の人にとっては、「何で2組が決めるんだ!」と思うでしょう。ここでは、きまりを決める人達(2組の生徒)ときまりに従う人達(1組の生徒)とがズレているので、2組で決めるべきことではないといえる。自己統治になっていないわけだ。
では、「2 クラスの生徒一人ひとりの所属するクラブ活動」はどうだろう?
例えば、B君は、野球部に入りたいと思っていたのに、クラスの多数決で、「B君、キミは、ちょっと太っているから相撲部に入りなさい。」なんて決められるなんて、何かおかしいよね。B君にとっては余計なお世話だ!という感じだろう。
どのクラブ活動に入るのかは、それぞれ個人に関することで、他の誰かが、決めるべきことではない。クラス全体に関わることではない。個人の判断にまかされるべきことだ。
個人一人ひとりの判断にまかされるべきことについては、その個人が属するクラスにおいても、多数決では決めるべきではないといえる。
では「1 文化祭でのクラスの出し物」について、みんなで、多数決できめてよいということだった。そこであるクラスは出し物を「ブレーメンの音楽隊」と決めた。そこで配役(ロバ役、犬役、猫役・・・)を決めるのですが、配役について、「ロバは絶対嫌だ!」といっているA君に、みんなで多数決で、「ロバ役にはA君がぴったり!」なんて、A君をロバの役にしてしまってよいのかな(①の問題)?
クラスの出し物の配役をどうするかは、クラス全体の問題。そうすると、クラス全体に関することなのだから、クラスのみんなの多数決で決めていいようにも思える。
でも、本当にそれでいいのかなあ?
A君以外の人達が、結束して「ロバ役はA君がいい」と票を固めれば、多数決でいいんだとするとロバ役はA君になってしまうことになる。
ひょっとしたら、周りからみるとロバ役にはA君がぴったりなのかも知れない。みんなはA君の演技力を評価してロバ役をA君に、と言っているのかも知れない。
でも「絶対嫌だ!」というA君の気持ちを無視してもいいのかな?
もちろん、ロバ役にはA君がぴったりだと思うから、A君よかったらなってくれないかな?とお願いするのはいいだろう。それでA君が、引き受けてくれるなら、めでたしです。
でも「絶対嫌だ!」といっているA君に対して、「そんなのA君の我がままだ!」「そんなA君の気持ちなんて関係ねえ。」と周りのみんなで、多数決で、無理矢理、A君に決めてしまうのは、やっぱり何かおかしいよね。
自分がA君の立場だったら、何ともいえない気分になるな。
一人ひとりの個人を大切にしないことになる。多数派で、特定の人に不利益を負わせることになりそうだ。
だから、多数決では決めてはいけないことだと思う。
②の教室の掃除当番を、女子だけで交替にやってもらうと多数決で決めるのもおかしいよね。そのクラスでは男子の数が女子の数より多く、多数決で決めるのであれば、男子が結束すれば、女子だけに掃除当番を押しつけるというきまりをつくることができるわけだ。
数の少ない女子だけに負担をかけるもので、公平ではない。多数派の男子が、少数派の女子に一方的に不利益を与えるもので、おかしいよね。平等でない。
だから、これもやはり、こんなきまりを多数決で決めることはできない。
「多数決でも決めていけないこともある」
「特定の個人や少数者に不当に不利益を与えたり、個人の判断にまかされるべきことについては、多数決で決められない」
ということを知っておいて欲しい。
もしキミ達が、クラス会とかで、何かを決めようとするとき、
「これってみんなで、多数決で決めていいことなのかな?」
「これを決めることで、特定の誰かに、不利益を押しつけようとしていないかな?」
ということをどこか頭の片隅において欲しい。
難しいことかも知れないけれど、とても大切なことなんだよ。
第5 民主主義と立憲主義2-表現の自由がない世界
前回、クラス会を題材にして、多数決で決めていけないこともあるんだよ、という話をした。
では、スケールを大きくして、国の場合、国会の場合はどうだろう。
国会では、法律は国会議員の多数決によって決められているが、多数決で決めるのなら、どんな法律であっても定めてもいいのだろうか。
例えば、こんな法律はどうだろう?
「国の政治を批判した人は刑務所に入れる」
こんな法律を、みんなによって選ばれた代表者(国会議員)が多数決で決めてよいのだろうか、多数決でも決めてはいけないことだろうか?
国会議員は、国民の選挙で選ばれた代表者ですから、その人達が、話し合って多数決で決めることなら、それが国民の意思じゃないの、国民の多数にそうものだから、何でも法律で決めていいんじゃないの?
そう思う人もいるかも知れないね。
王様や将軍のような特定の人が、勝手に決めた法律は問題だけど、国民の選挙によって選ばれた人なら、自分たちが選んだ人が、話し合って多数決で決める以上は、問題ないんじゃないの「正しい」んじゃないの。それが民主主義というものなんじゃないの?
総理大臣や、政府の人が
「私達の政権運営を批判する人がいる。私達がやっている政治は、国民のためにやっているのに、正しいのに、それを邪魔するのはけしからん。私達の政治を批判する人は、国家・国民の利益を損なう人でもあるから、処罰して、批判させないようにしよう。そうすれば、正しく美しい政治が円滑にすすむ。」
だなんて考えて、こんな法律を国会で作ろうとしています。国会では、総理大臣の政治に賛同し、「総理の考える政治の流れを止めていけない。」「反対派は、邪魔者だ。」「政治を批判するような少数派は、つべこべ言わず、政府の考えに従っていればいいのだ。」と考えている国会議員が多数でした。
多数決でどんな法律も決められるのなら、こんな法案も成立してしまうかも知れませんね。
どうだろう?こんな法律をつくってもいいのかな?
まずいよね。困るよね。
国の政治をおかしいなと思っても批判することができなくなる。表現することの自由が奪われることになる。怖くて言いたいことが言えなくなる。監視の目を気にして、冗談も言えなくなってしまう。
「表現の自由」は、憲法の世界では、とても重要な自由、大切な基本的人権とされている。
政治を批判することができない、政治を批判的に論じることができない世界って、どんな世界だろう。国家がやることに批判ができず、従順に従い、褒め称えるしかない世界ってどんな世界だろう。
「それって、おかしいんじゃない?」って声を出すことができない世界。
「私は、政府のやり方より、こうした方がいい。」と言えない世界。
一体どんな世界なんでしょう。人々はどんな暮らしをしているのでしょう。
少し想像力を働かせてみましょう。
表現の自由のない世界ってどんな世界なんだろう?
テレビや新聞は、国の政治をほめたたえる報道しかしません。
政治や権力にとって不都合な事実は報道しません。国会議員や公務員の不祥事なんて明るみにでません。
だから、国民は、生活は苦しくても、不自由な暮らしを送っても、国の政治に問題があるとは思わない。もし思っていても、国の政治に問題があるなんて言えない。
学校の先生も、国の政治は素晴らしいと子どもたちに教育する(そういう人しか学校の先生になれませんし、学校にいられません)。
暮らしに不満があっても、それは自分とは違う考え方の人たちのせい、どこかの国のせいだと思うかも知れません。
一見、統一化、画一化かされ、統制がととのった見た目はきれいな感じになるかも知れないね。
見た目は美しい。一致団結。統制のとれた集団。そこでは、多様性は否定される。異質なものは排除される。少数者の利益は無視される。
そんな流れになってきそうだ。
画一化された人々は、国家からの情報をもとに、国家を中心に、きれいにまとまっていくことだろう。
実は、一人ひとりの幸せや良心は置き去りにされたことに、気がつかないままに・・・。
自分で自分の幸せを追求することの感覚がマヒしていく。「これが国民の幸せなんだから、こうしなさい。」と幸せを国が教えてくれるから「そうなのかなあ」って思い込むことだろう。
画一化され、多様性が否定され、ベクトルの方向が一つにまとまった時、その方向へ、ぐんぐん進んでいく。加速していく。暴走していく。
国民の多くも気分は盛り上がってくるだろう。「正義は我らにあり!」とか「平和のために、敵をやっつけよう!」なんて勇ましい気分になってくるだろう。
国家(=権力)も、自由にものが言えない世界で、つくりあげられた国民の多数=世論に乗っかって、どんどん加速していく。
こうして、国家(=権力)が暴走してしまっても誰も止めることはできないだろう。暴走してしまっている時に、内心で「あれ、ちょっとこれは違うんじゃないかな。」「一体何のために、私達は、人を傷つけ、人から傷つけられたりしているのかな。」と疑問に思っても止められいだろう。
国民が、政治の批判も含めて、言いたいことを言える自由がなかったとしたら、とても怖い世界になりそうだね。
実際、戦争につきすすんだ昔の日本では、これと似たような法律があって、国の政治を批判した人達が捕まり、批判することがおさえつけらたんだ。
また、独裁国家では、これとにたような法律がある。
権力を掌握し、権力を維持、拡大する者にとっては、国民の「政治を批判すること」こそ苦々しいものはないからね。従順にロボットのように従ってくれる国民こそ「よい国民」だろう。
権力をもつ者は、その性質上、批判されるのが苦手なんだ。できれば批判されたくない。そんな世界では、一人ひとりの幸せは、大切にされない。多くの人と違うこと、多くの人の考えと違うことは、嫌がられる。「そんなのわがままだ。」と一蹴されそうだ。
みんなと同じ考え、みんなと同じ価値観、みんなと同じ好み、そうなるよう圧力がかかってくる。そしてみんな=国の考えとなっていく。
自分の幸せは自分で決め、求めていく。
自分のなりたい人になる。
好きなことを仕事にする。
やりたいことをやる。
そして、自分の良心に従って生きる。
そんなことは夢物語になるのかも知れないね。
かつて、言いたいことがいえないことがあり、それで戦争につきすすんでしまった、戦争で多くの人々が悲惨な目にあったことをふまえて日本国憲法は「表現の自由」を大切な人権として、定めた。
憲法第21条
集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
先に、国家(=権力)はとても大切なものであるが、間違ったり、暴走して、国民個人の自由や権利を侵害してしまうものなので、憲法で、国家=権力を縛る、コントロールするという話をした。
国家(=権力)を縛るという意味で、表現の自由は、とても重要な意味をもっているんだ。
国の政治や総理や国会議員の発言についてありのままに報道し、国民に情報を与えること。そして、国民が国の政治について意見を言い、「これはまずい」「こうした方がいい」と言えること、こうしてはじめて、国民が、国家=権力をコントロールすることが可能になってくる。
国家からの一方通行ではなく、国家と国民の双方通行が成り立つ。
国家(=権力)の間違いや行き過ぎにブレーキをかけることが可能になってくるんだ。
そして、表現の自由は、民主主義を支える自由として、大切なんだ。
みんなが言いたいことが言える、批判したりできることで、話し合いの場で、いろいろな意見がでてくる。多数派の人だけでなく、少数派の人も、どうしてそう考えるのが自分の意見を言うことができる。少数派の人の意見を聞くことで、多数派の人の意見も変わるかもしれない。また少数派の人の意見をふまえたルールを作ることができるかもしれない。
言いたいことを言える自由、表現の自由があってこそ「みんなのことは、みんなで話し合って決める」という民主主義が実現される。
みんなが自由に意見が言えない状況で、安易に多数決で決めるというのでは、本当の民主主義は実現されない。
表現の自由は、こんなにも大切な人権だから、憲法は、国家(=権力)に対して「これは、大切な人権だから、侵害してはダメですよ。守りなさいよ。」と縛りをかけているんだ。
憲法は「あなた(国家=権力)は、放っておくとすぐ人々の表現の自由を制約しがちで、実際にも昔、言論を抑圧して、人々がとんでもない目になったことがあるでしょ。だから特に気をつけなさいよ!」と憲法は、国家にこの表現の自由を「侵害しちゃダメだよ!」と縛りをかけているんだね。
国家は、法律を作るときに、国民の表現の自由を侵害する法律を作ることは、許されない、もし間違ってそんな作ってしまっても「無効」とすると憲法は、国家を縛っている。
それは、国民一人ひとりの表現の自由を守るために。
そして、国民一人ひとりの存在を大切にするために。
ですから、「国の政治を批判した人は刑務所に入れる」というような法律を国会で作ってはいけません。憲法に違反することになります。
第6 民主主義と立憲主義3-どちらも個人の尊厳をまもるために
法律は、国民から選挙で選ばれた国会議員によって、議論され、多数決によってきまるもので、民主的な基盤がそこにある。
そんな民主的な基盤があっても、民主主義にそっていても、「国の政治を批判した人を刑務所に入れる」というような表現の自由を侵害するような法律は、決めてはいけない、多数決でも決められないということだった。
憲法は、この「表現の自由は、大切なものだから、国家は制限してはいけないよ!」と国家に縛りをかけているんだね。
国家に縛りをかけるという考え方を立憲主義といいますが、国民の代表者からなる国会で多数決で決められないこともあるということは、立憲主義が、民主主義を制限しているという関係に立つといえそうだ。
民主主義の目的は、国民一人ひとりを大切にするために、みんなの意見を反映させるということでしたが、いろいろな人がいて、どうしても多数派と少数派と別れてしまうこともありえます。
そして、多数決の場面で、多数派の意思にもとづいて国家や団体の意思決定がなされることになります。
そんな時、特定の少数の人に、一方的な不利益を与えてしまうかも知れません。負担を押しつけてしまうかも知れません。
多数派の人は、往々にして、少数派の気持ちは分からないものです。
そして、気持ちが分からないまま多数決によって、少数者の人の大切な自由を奪ってしまうかも知れません。
ナチスドイツのヒトラーって知っているかな。
ユダヤ人の大虐殺とか、他国の侵略をした独裁者だね。
ヒトラーは、突然独裁者になったわけではなく、国民の大多数の指示を受けて、権力者の地位につき、その政策を推し進めました。民主主義にのっかっていたわけなんだ。
でも、あのように自国民も他国の人にも大きな犠牲がでる結果となった。
民主主義は、絶対ではない。それだけでは間違ってしまうこともある。そして、間違ってしまったとき、大変悲惨な結果も起こりうる。
そんなことがないように、憲法は、多数決でも奪ってはいけない人権のリストをかかげた。表現の自由、信教の自由等の人権は、人が人として生きていくのに大切なものだから、多数決=法律でも、侵害することを決めてはいけないことにした。民主主義に制限をかけた。
憲法は、民主的な基盤をもつ国家(=権力)に対しても、「この権利、自由は、人権つまり人が人として生きていくために大切なものだから、侵害しないように注意せよ。」と縛りをかけているのだね。
そうすることによって、時に、多数決によって、侵害されることもある個人、特に少数者の人権を守ろうとしている。
キミは、「民主主義」って聞くと、正しいもの、いいもの、間違いないものって感じがしないかな?
「民意」とか「世論」というのはどうだろう?それには当然従わなくちゃいけないって感じにならないかな?
でも、与えられた情報とか、なんとなくといったムードとかで、「あの国(あの団体)感じ悪い、怖い、気に入らない。」といったような雰囲気が生まれ、多数意見が形成される可能性は否定できないだろう。
そしてナチスドイツや戦争につきすすんだ過去の日本の経験も踏まえて「民主主義は絶対ではない」としたところに、憲法の大きな意味があるんだ。
おそらく「民主主義=正義、絶対」となりがちなところだと思うので、実は、そうではないんだ、限界もあるんだということを是非知っておいて欲しい。
日本国憲法の究極的な目的は、個人の尊重(個人の尊厳)、つまり一人ひとりをかけがえのない存在として、個人として大切にすること、にある。
憲法第13条
すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。
では、個人の尊重を確保するためにどうすればよいか?
歴史上、個人の尊重を踏みにじってしまったのは、国家(=権力)だった。
国家(=権力)は、安全を確保したり、社会秩序を維持したり、人と人との自由を調整したり、国民一人ひとりにとって大切なもので、必要なものだ。
だけれども、国家(=権力)は、その性質上、強大な権限、強制力があり、また強くなろう、大きくなろう、批判されたくないといった性質があるために、歴史上、間違ったり、行き過ぎたりして、個人の尊重を踏みにじってしまったこともあったんだ。
いや、本当のところは、現在もいろいろなところで、間違い行き過ぎは起きているのだろう。例えば、無実の人が刑務所に入れられてしまうという「えん罪事件」はまだ起きている。
だから、憲法は、国家(=権力)に対して向けられている。
国家(=権力)が、個人一人ひとりの個人の尊重を害さないように、国家が奪えない権利自由を人権のリストとして、憲法に掲げているのだね。
立憲主義は、民主主義を制限するものということだが、他方で、立憲主義と民主主義は、いずれも、個人の尊重確保のためのものといえる。
つまり民主主義は、国家権力自体を、国民の意思が反映され、国民がコントロールるようなシステム、権力に民意を反映するシステムによって、権力による人権侵害をおさえようとしている。
国民自らが、権力について、影響を与え、批判を加え、権力側に参加する道もあるということで、自らの権利自由を制限しないようなルールをつくっていけることになる。
王様のような特定の人が決めるのと国民の選挙によって選ばれた代表者が話し合って決めるのとでは、どちらが国民個人の権利や自由にとって、よい法律が作られるかどうかを考えてみると分かるだろう。
少数派の人達も、議論の中で自分の意見をいい、多数派の人達も少数派の人達の意見をよく聞くことで、個人の尊重、少数者の人権を無視するような法律やルールを作ることを一定限度は防ぐことができるだろう。
この点で、民主主義は、立憲主義と相携えながら、車の両輪のように、個人の尊重確保を支えていると言える。
それに、前回、お話しましたが、表現の自由は、民主主義を支えるものなんだ。自由な情報の流通があり、国政への批判も含めて、自由に話し合いができるからこそ、民主主義が維持できる。
だから、表現の自由をふくめた人として大切な権利自由をまもろうとする立憲主義は、民主主義を支えるという関係にも立つのだね。
まとめると
「立憲主義は、民主主義を支え、しかし、時に制限する。そして、立憲主義と民主主義は、ともに個人の尊重をまもるための車の両輪である。」
ということなんだ。
第7 憲法と法律って何が違うの?
キミは、憲法と法律ってどこが違うのかわかるかな?同じじゃないの?と思う人もいるかも知れないね。
でも違うんだよ。憲法と法律ではレベルが違う。格が違うんだ。憲法は法律ではない。
憲法は、最高法規として法の頂点に君臨し、憲法に反する法律は無効とされる。
憲法第98条1項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律・・・は、その効力を有しない」
とされている。
どうして憲法が法律を無効にするほど偉いのかといえば、憲法が、日本国民の基本的人権を保障し、基本的人権を侵害しがちな国家を縛る役目を持っているからなんだ。憲法は国家に向けられた権利章典だから偉いんだ。
憲法第97条
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」
そして、憲法が、主権者である日本国民によって確定されているものだから偉いんだ(「国民主権」ということだね。)
立憲主義のところで話たけれど、憲法は、個人の尊重を最大の価値とし、基本的人権を確保するために、「国家を縛ること」を目的としている。
国家によって、人権が侵害されてきたという苦い経験があったことをふまえ、国家を縛ることが人権確保にとって必要不可欠だとされた訳だね。
他方で、法律は、国会(衆議院と参議院)で成立するものだけど、法律制定の目的の根底には、国家が社会秩序の維持のために、人々の間の権利自由の調整のために、特定の個人の権利自由を制約するものなんだ。国家が国民を縛っている。
憲法と法律とでは、「縛る」主体と客体が入れ替わっている。「縛る」方向、矢印が正反対なんだ。
憲法は 国民が国家を縛る(コントロールする)
法律は 国家が国民を縛る (コントロールする)
いずれもその究極の目的は、憲法が定める「基本的人権の保障」にある。
人は一人で生きていくわけでなく、社会の中で、いろいろな人とつながりを持ちながら暮らしている。
それぞれ違った人、違った価値観がいる中で、つながったり、ぶつかったり、交渉したり、物を交換したりする。1人の自由が、他の人の自由や権利を侵害することもある。周りの多くの人にとって迷惑なことになることもある。
みんなが好き勝手なことをしてしまうと、結果として社会は混乱して、みんな不幸になってしまう。
それを調整し、時に強制力をもって制止するのが国家、法律の役目だ。
憲法第13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
つまり国家や法律は「公共の福祉」を考えて、個人の権利自由に一定の制約をして、権利と権利の調整、社会秩序維持を図ることを目的としている。
「公共の福祉」というのは、自分にも権利や自由があるように他の人にも権利や自由があるから、何をしてもいいという訳ではなくて、他の人の権利や自由と調整して、権利や自由が制約させることもあるということだ。
でも、権利と権利の調整を図り、社会秩序の維持を図る法律であっても、その究極の目的は、あくまでも「個人の基本的人権を確保するために」であって、その「手段」として他者の権利自由を奪うような人の自由に制約を課しているのだ。
個人の権利自由を制限することそれ自体が目的はないということは忘れないで欲しい。
そして、国家が国家の利益のために、ましてや一部の政治家や企業のために法律があるわけではないんだよ。
憲法と法律は、「縛る」主体や客体、方向性が違うこと、でも、どちらも究極は「個人の尊重、個人の基本的人権を確保するために」という価値を実現するためのものであることを知っておこう。
(おしまい)
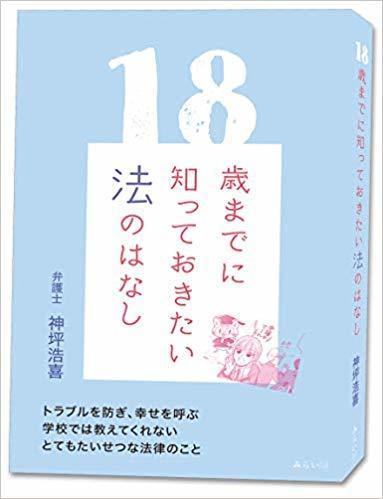
私が、中学生、高校生に向けて法について、語りかけるように書いた「18歳までに知っておきたい法のはなし」(みらいパブリッシング)が、全国の書店で発売中です。
中学生・高校生がスラスラと読めて、法について楽しく学べるように書きました。はじめて法を学ぶ大学生の入門書にもいいと思います。
ぜひ、読んでみてくださいね。合格祝い、卒業祝い、入学祝いやこれから一人暮らしをはじめるお子さんへのプレゼントにもいいとおもいます!
Amazonのページはこちら
(目次)
はじめに
第1章 そもそも法って何?~いろいろな人がいる社会の中で幸せに生きる仕組み
1 法と幸せ
2 ルールはなぜ必要?
3 よいルールの条件とは?
4 正義って何?
コラム)桃太郎は正義の味方か?
第2章 僕たちは憲法のもとに生きている
1 民主主義と立憲主義のはなし
(1)民主主義って何?
(2)民主主義って多数決のこと?
(3)憲法は、国家を縛る~立憲主義
(4)表現の自由がない世界
(5) 民主主義と立憲主義-個人の尊厳をまもる
2 権力分立~権力の濫用を防ぐためのシステム
3 ジョン・ロックのはなし~国家、自然権、法の支配
4 国民主権って何?
(1)主権が国民にあるってどういうこと?
(2)18歳になったら選挙権行使!
5 基本的人権の尊重~憲法は人権のカタログ
第3章 裁判員になっても大丈夫?~刑事手続
1 弁護士はなぜ「悪い人」の弁護をするの?
2 逮捕されてしまった!その後どうなる?
3 犯罪と刑罰のはなし
(1)犯罪って何だろう?
(2)どんな刑罰があるのだろう?
(3)死刑制度について考えてみよう
(4)なぜ刑罰が必要なのだろう?~刑法の目的
4 刑事手続
(1)いきなり「刑務所行き」にはできない
(2)なぜ、被疑者、被告人には黙秘権があるの?
5 検察官の役割
6 弁護人の役割
7 無罪推定の原則~疑わしきは被告人の利益に
8 もしも君が裁判員に選ばれたら~裁判員として知っておきたいこと
(1)裁判員とは?
(2)裁判員になるまで
(3)裁判員として審理に立ち会う
証拠に基づく事実認定を行う
量刑~被告人に言い渡す刑をどうする?
第4章 大人になる前に知っておきたい契約・損害賠償のこと~契約、市民生活に関する法
1 契約って何?
2 どんな契約も守らないといけないの?
(ア)契約の拘束力にも例外がある
(イ)契約を解約できる場合
1)未成年者取消権
2)詐欺取消、強迫取消
3)債務不履行契約解除
4)合意解約
5)クーリングオフ
3 悪徳商法に騙されないために
1)ワンクリック詐欺
2)デート商法
3)マルチ商法
4 借金を返せなくなったらどうなる?
(1)お金を借りることの意味
(2)友達から「保証人」になってと頼まれたら
(3)もし借金に困ったら
5 働くときのルール ワークルール
(1)立場が弱い従業員を守るワークルール
(2)働く前に知っておきたいワークルール
1)労働時間
2)賃金
3)休暇
4)解雇のルール
(3)ブラック会社に気をつけよう
(4)セクハラ・パワハラで困ったら
6 損害賠償のはなし
(1)どんなときに損害賠償請求ができるのか?
(2)「損害の公平な分担」という考え方
第5章 交渉法を身につけよう!
1 交渉って何?
2 交渉のコツ
(1)準備が大切
(2)交渉の場で
①感情的にならずに冷静に伝える
②論理的に伝える
③相手の言い分をきく
④自分の言い分と相手の言い分とを整理する
⑤解決案を考える
第6章 トラブルに巻き込まれたら
1 弁護士に相談してみる
弁護士の探し方
いい弁護士の見分け方
2 調停というもめごと解決法もある
第7章 裁判所ってどんなところ?
1 裁判の役割
2 裁判傍聴に行ってみよう
3 裁判官という仕事
(1)裁判官の責任は重大
(2)裁判官ってどんな人?
(3)裁判官のやりがい、苦労
第8章 法的なものの見方・考え方を身につけよう!~大人の知的技能
1 主張(意見)に理由をつける
2 事実と意見を分ける
3 事実の中で、どういう事実が重要になるかを見極める
4 事実については、裏付ける証拠がないかを確認する。
5 論理的思考とは
おわりに
「個人の尊重」-何かを大切に思う気持ちに違いはないこと

仙台市泉区泉中央の弁護士2名(弁護士神坪浩喜 弁護士林屋陽一郎)の法律事務所です。借金相談(債務整理・自己破産・個人再生・過払金返還請求)、離婚相談、相続相談、交通事故相談等の無料法律相談を実施しています。お困りの方は、
「あやめ法律事務所」へ法律相談をお申込みください。誠実な対応を心がけております。
法律相談のご予約

お気軽にご相談ください。
お電話でのご予約はこちら
022-779-5431
相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで
メールでの受付は、24時間行っております(折り返しのご連絡は、基本的に上記受付時間となります)。
借金、相続、離婚、交通事故、不貞慰謝料の相談料は30分以内無料です。その他の事件は、30分あたり5500円です。
※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。
※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。
※取扱い地域
仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域
無料法律相談のご予約
コラム
- バーガー国ものがたり~3つのアイデア:自然権、社会契約、法の支配
- 他人と比べないこと(R3.11.15)
- 生きがいについて(R2.11.23)
- 所有権絶対の原則!(R2.4.6)
- 長男の妻の労苦は報われるのか?(R2.4.2)
- 配偶者居住権が新設されました(R2.4.1)
- パワハラをしないためには知識が必要です!(R2.3.25)
- こども六法(R1.9.24)
- 国民主権って何だろう?(R1.7.15)
- 裁判官はどのように判断しているのか?(R1.7.6)
- 自分の主観と相手の主観とはズレているもの(R1.6.30)
- 本当に怖いセクハラパワハラ問題(R1.6.22)
- 愛の本2 自分以外の人は全て他者(H31.2.10)
- 愛の本 他者との〈つながり〉を持て余すあなたへ(H31.2.3記)
- 自分の一番の味方は自分(H31.1.21)
- 友だち幻想3 人生の苦味・うま味(H30.9.9)
- 対人距離がわからない(H30.8.6)
- 正義とは他者に対する公正さ(H30.7.15)
- 人間関係に悩んだら、とりあえず「登場人物」を紙に書きだす(H30.6.12)
- 友だち幻想2 距離の感覚(H30.5.29)
- 友だち幻想 人と人のつなばりを考える①(H30.5.14)
- 主観的に大切なこと、客観的に重要なこと(H30.5.3)
- 自己開示の効用(H29.12.23)
- 人生は思うようにはならないもの(H29.9.21)
- 正義って何?~反転可能性テスト(H29.9.16)
- 悩んだら、とりあえず散歩(H29.6.25)
- 自分に価値があると思えるために2(H29.4.27)
- 自分に価値があると思えるために(H29.3.5)
- 3人のレンガ職人(H28.9.26)
- よく生きるために働くということ(H28.9.18)
- 弘前の桜(H27.5.8)
- 取引先破綻の商品引き上げについて
- ずっと運の悪い人はいませんよ。
- 第○回の調停を始めます! (H26.8.30)
- 複数のスポーク
(H26.8.14) - 嫉妬心とのつきあい方(H26.7.27)
- 本当は仲直りがしたいのに (H26.6.15)