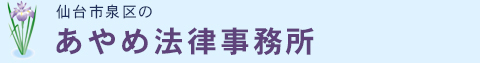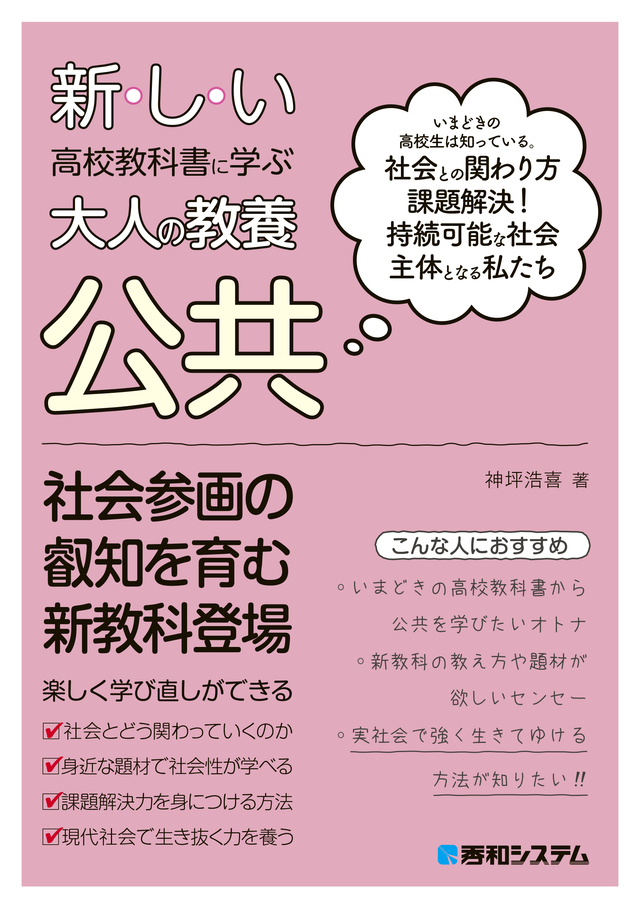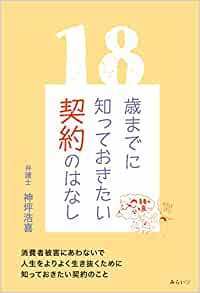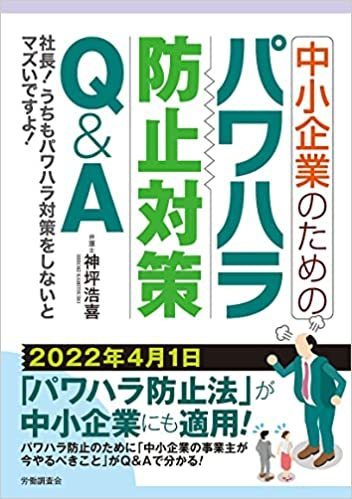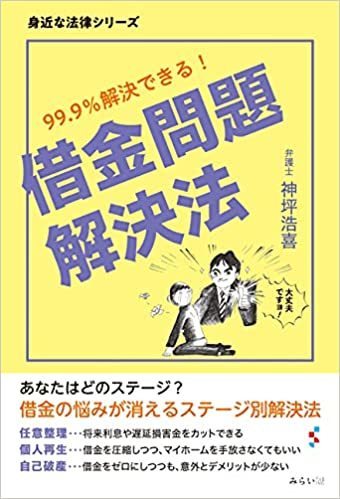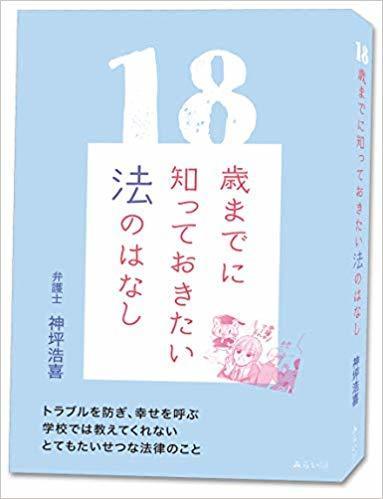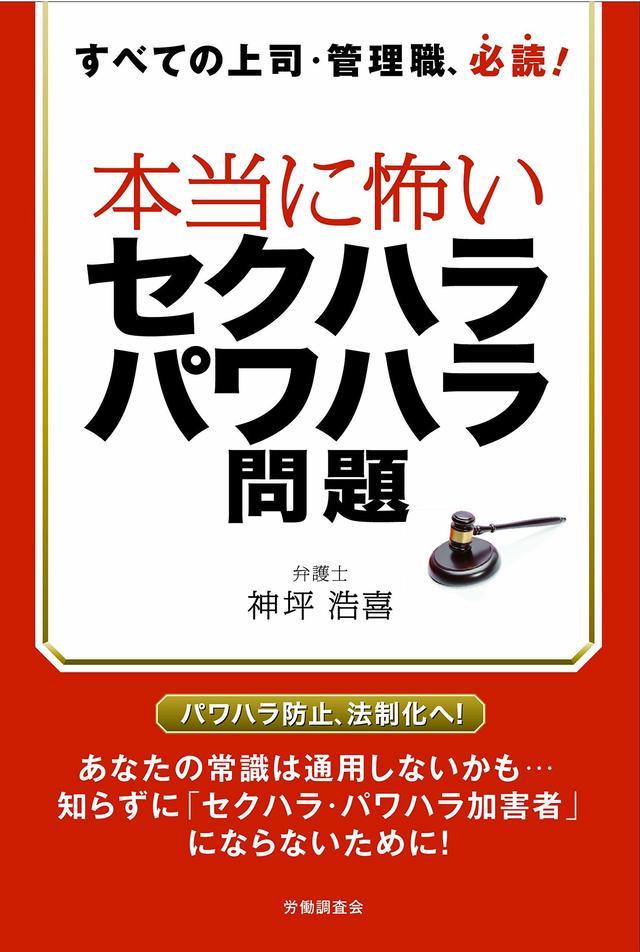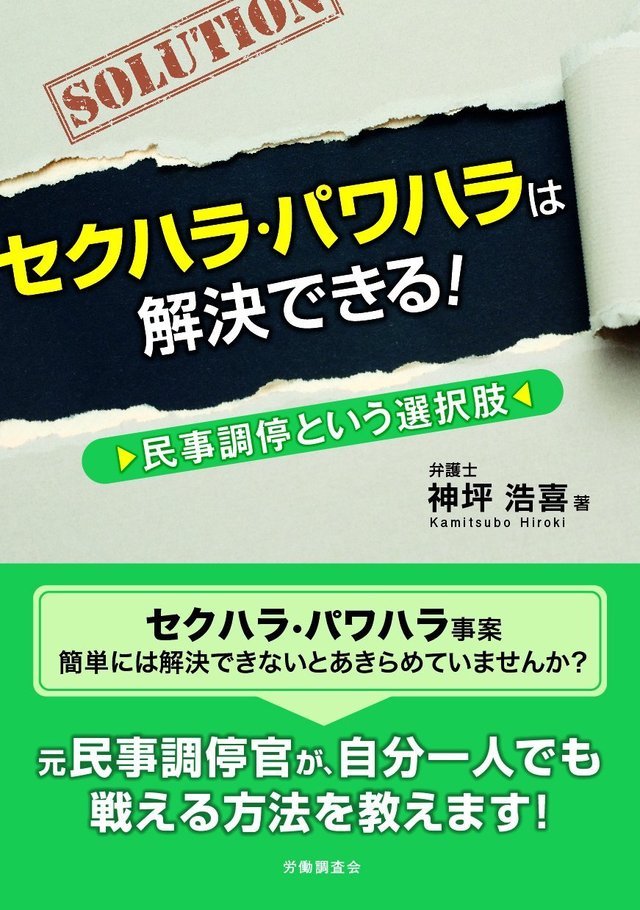宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
<お電話での相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後0時20分
午後1時20分から午後5時15分まで
メールでは24時間受付
子どもの自転車事故と親の法的責任
弁護士 神坪 浩喜
1.はじめに
宮城県では平成17年以降、自転車事故は減少傾向ありますが、平成25年9月末現在における自転車交通事故件数は944件、うち6件で死亡事故が発生しています。
道路交通法では、自転車は自動車と同じ「車両」の扱いであるため、自転車運転者は自動車運転者と同様、道路交通法の様々なルールを守って走行しなければなりませんし、事故の加害者となれば、多額の民事賠償責任や刑事責任が追及されることになります。
子どもの交通手段としての大部分を占める自転車ですが、もしも子どもが自転車事故により加害者になった場合、その責任は子どもの監督者である親に追及されることになります。近似の判例をもとに、その実情を見ていきたいと思います。
※平成25年7月4日神戸地裁判決の概要
当時小学5年生(11歳)男児が運転する自転車が歩行中の女性(当時62歳)をはね、未だ被害者女性は意識不明の状態が継続している事件において、平成25年7月4日、神戸地裁は、男児の母親に対し、約9500万円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。
判決は、本件事故が、男児が「自車の前方を注視して交通安全をはかるべき自転車運転者としての基本的注意事項があるにもかかわらず、これを尽くさないまま、しかも相当程度勾配のある本件道路を速い速度で走行し、その結果、衝突直前に至るまで」被害者女性に気付かなかったことによって発生したもの、と認定しました。さらに、男児は事故当時11歳の小学生であり、責任能力がないと認めた上で、本件事故により被害者(本件事故では自動車保険会社に対する損害も含む)に生じた損害については、民法の規定(本件では714条)により、男児の唯一の親権者であり、男児と同居して監護にあたっていた母親が負うものと結論づけました。

2.子どもが起こした事故に対する
「親の責任」とは?
自転車や自動車により交通事故を起こし、被害者に何らかの損害を与えてしまった場合、被害者が民事責任として損害賠償を請求してくることがあります。その請求の根拠となる条文が、民法709条、不法行為責任に関する条文です。
民法709条が定める民事責任(損害賠償責任)は、成人に対してはもちろんのこと、未成年に対しても追及することができます。しかし、自分の行った行為の結果について法的に責任があるか否かの判断が十分にできない子どもにまで右責任を追及するのは非常に酷なことです。
そのため民法は「責任能力」という判断基準を置き、責任能力が認められない子どもの行為によって発生した損害については、その子どもの監督を怠った親に追及し、被害者を保護しようとする仕組みが採用されています。これを規定する条文が714条です。
つまり民法は、子どもの親権者や、親権者の代わりとなって子どもと日々生活し、養育・指導している大人(育ての親、親族など)が、その子どもが他人に損害を与えるような危険な行為をしないように日々監督・指導する義務(監督義務)を負っていることを前提としており、その義務を怠った監督者は、責任能力がない子が起こした損害についての責任を免れることはできないという理論を採っているのです。上記判決も、この理論により男児の母親の責任を認めています。
ちなみに、小学校を卒業する12~13歳程度になれば一般的に責任能力があると認められていますが、責任能力がある子どもが起こした交通事故についても、いまだ親に責任を追及することができる可能性はありますので注意が必要です。
3.民法714条の責任を免れるためには…?
民法714条の損害賠償の根拠は、先に述べたとおり、監督義務者がその監督義務を怠ったことに求められ、その子どもが何か特定の違法行為をすることそのものを予防しなかったことではなく、より抽象的な子どもの行動一般に対する監督義務を怠ったことにもとめられます。そのため、裏を返せば、子どもの行為によって他人に損害を与えてしまった場合でも、その子どもへの監督義務を怠らなかったことを証明することによって、監護者は免責を受けることができます。
しかし、その証明は容易ではありません。子の行動一般に対する監督義務はかなり広範であり、やはり子どもの行為によって生じた損害に対しては、親が責任をとるべきという要請にはなお強いものがあるため、不可抗力などの事情や、損害発生の予測が極めて不可能な事件であったなどの事情がない限りは、免責を受けるのは非常に難しくなると思われます。
上記事件では、母親が、男児に対して日常的に自転車の走行方法について指導するなど監督義務を果たしていた旨を主張していましたが、男児の行為態様や注意義務違反の内容・程度を見る限り、母親による指導や注意が奏功していたとはいえないことから、男児に対する自転車の運転に関する十分な指導や注意をしてはいなかったとして、裁判所は母親の免責を認めませんでした。
以上のとおり、事故を起こしてしまった以上は、特別な事情が存在しない限りは、その責任を負わざるを得ませんし、それが当然のことと思います。自転車事故そのものを起こさせないよう、親子ともに危機感を持ち、ルールを守った自転車の利用を心がけることが大切であると思います。
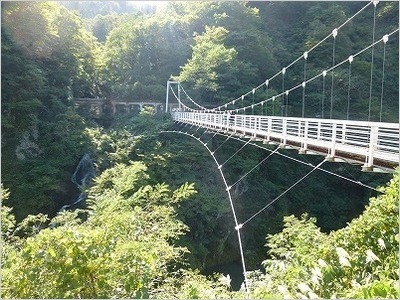
4.自転車保険の加入について
平成25年7月4日判決では、加害者側に対し、被害者、自動車保険会社への計9500万円の損害賠償命令が下されましたが、この額は決して珍しいものではありません。被害者が被った損害を法的に評価してその賠償額が決定されるので、被害者が死亡した場合や、上記の事件のように昏睡状態が続いている場合、後遺障害が残った場合などはかなりの高額になるでしょう。また、自転車も自動車と同じ「車両」扱いですから、自動車の場合よりも賠償額が低くなるとは限りません。過失によって与えた損害については賠償する責任があるのです。上記判決が出た後、自転車事故に対応した保険の加入者がぐんと増えたという話も耳にします。
万が一に備えて、できれば自転車保険に加入することをお勧めします。現在では、「交通事故傷害保険」と「個人賠償責任保険」がセットになった自転車保険が多く販売されています。そちらを新たに加入するという考えもありますが、他人に損害を与えてしまった場合に保証金が支払われる「個人賠償責任保険」については、自動車保険や火災保険の特約として販売している場合もあるので(共済にもそのような特約があるようです)、そちらを既存の保険契約に加えるという方法もあります。
また、自動車安全整備士に点検整備してもらった際に貼ってもらえる「TSマーク」(2種類あります。点検整備の金額によって異なります)にも保険が付帯されています。TSマーク付帯保険は、TSマーク付自転車搭乗者が交通事故により障害を負った場合に適用される「障害補償」と、マーク付自転車搭乗者が第三者に障害を負わせてしまった場合に適用される「賠償責任補償」の2つをカバーしています。
この付帯保険は、点検整備をし、シールを貼ってもらった日から1年間有効で、このシールが貼ってある自転車に搭乗している場合(押して歩く場合も含む)ならば補償が適用されますので、その自転車の所有者に限らず、他人が乗った場合にも保険が適用されます。
しかし、決められた補償額は任意の保険よりもかなり低くなりますので、できれば任意保険にも入っておいた方が安心です。
ただ、シールの期限の更新に合わせて毎年点検整備することで、整備不良による事故の予防には大きな力を発揮するものと思われますし、危機管理の意識を保ち続けるよい機会になるとも思います。
5.おわりに
以上のとおり、自転車事故で加害者になった場合、自動車と同じ法的責任が追及されることになります。また、対自動車との交通事故においては、自転車運転者自身の生命が危険にさらされることになります。
自転車だからと甘く見ずに、自転車事故を起こさない、そのためにはどのような利用を心がけなくてはならないのか、もう一度、親子一緒に話し合ってみてはいかがでしょうか。
法律相談のご予約

お気軽にご相談ください。
お電話でのご予約はこちら
022-779-5431
相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで
メールでの受付は、24時間行っております(折り返しのご連絡は、基本的に上記受付時間となります)。
借金、相続、離婚、交通事故、不貞慰謝料の相談料は30分以内無料です。その他の事件は、30分あたり5500円です。
※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。
※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。
※取扱い地域
仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域
無料法律相談のご予約
コラム
- バーガー国ものがたり~3つのアイデア:自然権、社会契約、法の支配
- 他人と比べないこと(R3.11.15)
- 生きがいについて(R2.11.23)
- 所有権絶対の原則!(R2.4.6)
- 長男の妻の労苦は報われるのか?(R2.4.2)
- 配偶者居住権が新設されました(R2.4.1)
- パワハラをしないためには知識が必要です!(R2.3.25)
- こども六法(R1.9.24)
- 国民主権って何だろう?(R1.7.15)
- 裁判官はどのように判断しているのか?(R1.7.6)
- 自分の主観と相手の主観とはズレているもの(R1.6.30)
- 本当に怖いセクハラパワハラ問題(R1.6.22)
- 愛の本2 自分以外の人は全て他者(H31.2.10)
- 愛の本 他者との〈つながり〉を持て余すあなたへ(H31.2.3記)
- 自分の一番の味方は自分(H31.1.21)
- 友だち幻想3 人生の苦味・うま味(H30.9.9)
- 対人距離がわからない(H30.8.6)
- 正義とは他者に対する公正さ(H30.7.15)
- 人間関係に悩んだら、とりあえず「登場人物」を紙に書きだす(H30.6.12)
- 友だち幻想2 距離の感覚(H30.5.29)
- 友だち幻想 人と人のつなばりを考える①(H30.5.14)
- 主観的に大切なこと、客観的に重要なこと(H30.5.3)
- 自己開示の効用(H29.12.23)
- 人生は思うようにはならないもの(H29.9.21)
- 正義って何?~反転可能性テスト(H29.9.16)
- 悩んだら、とりあえず散歩(H29.6.25)
- 自分に価値があると思えるために2(H29.4.27)
- 自分に価値があると思えるために(H29.3.5)
- 3人のレンガ職人(H28.9.26)
- よく生きるために働くということ(H28.9.18)
- 弘前の桜(H27.5.8)
- 取引先破綻の商品引き上げについて
- ずっと運の悪い人はいませんよ。
- 第○回の調停を始めます! (H26.8.30)
- 複数のスポーク
(H26.8.14) - 嫉妬心とのつきあい方(H26.7.27)
- 本当は仲直りがしたいのに (H26.6.15)