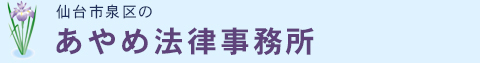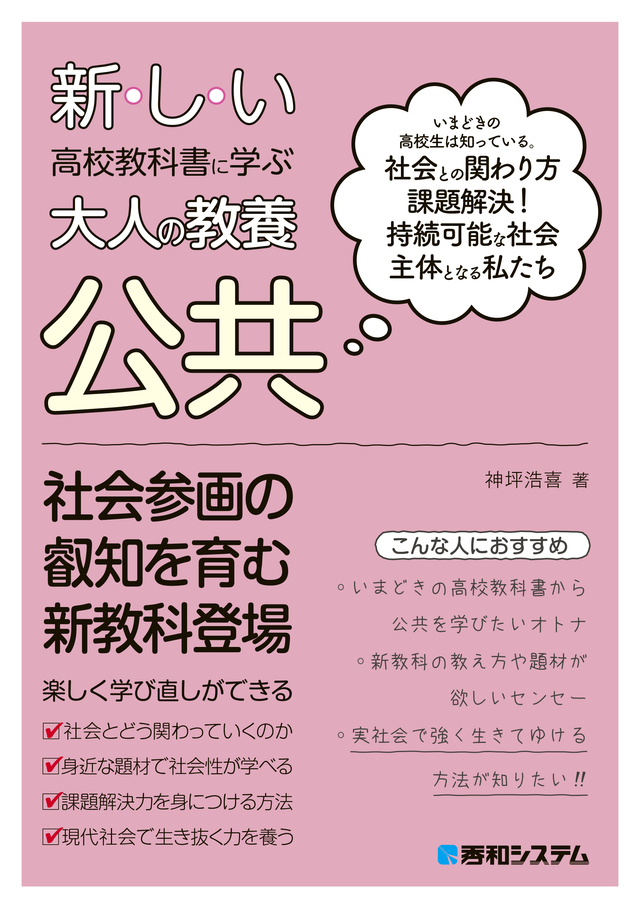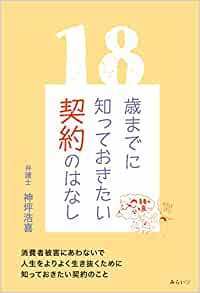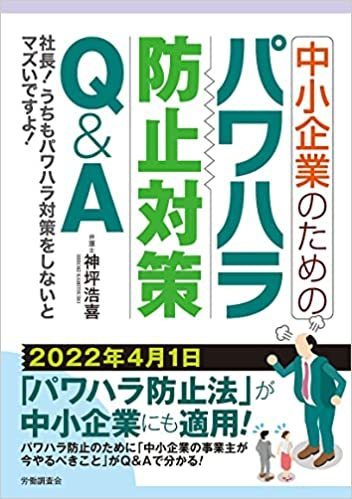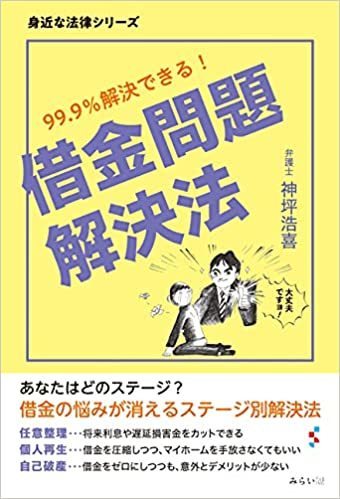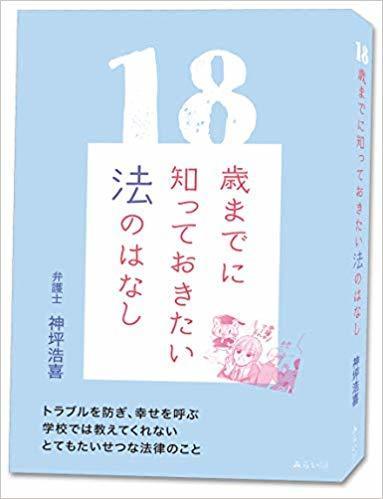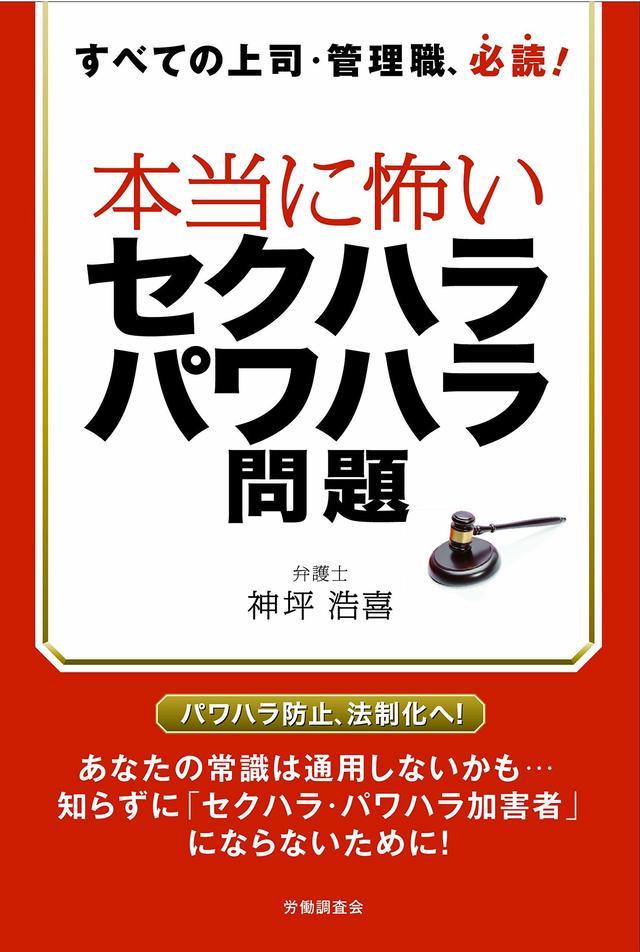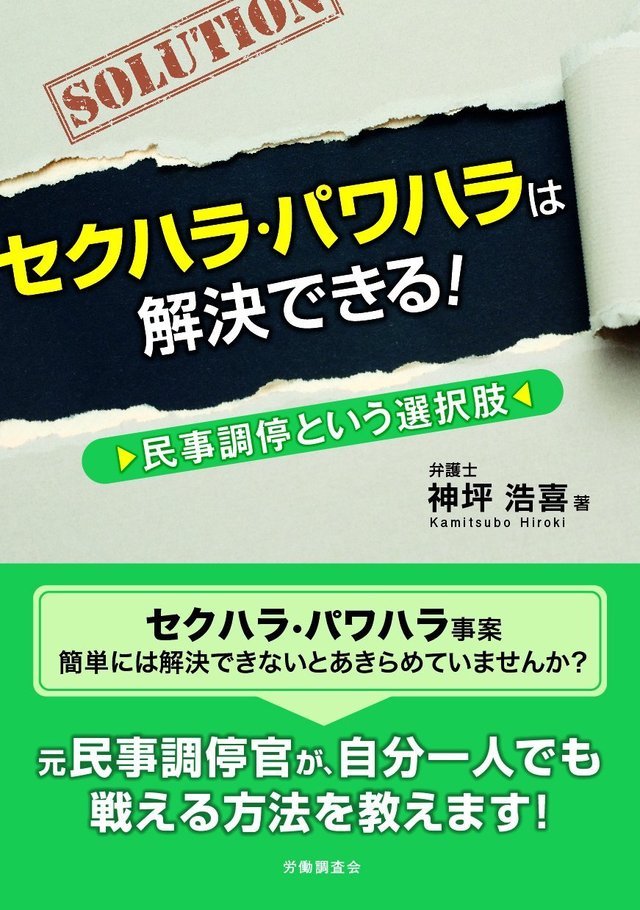宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
<お電話での相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後0時20分
午後1時20分から午後5時15分まで
メールでは24時間受付
民事調停について思うこと その1 真意を確認する

平成24年1月10日(月)
こんにちは。
神坪浩喜です。
妻が買ってきた「おみくじクッキー」が末吉だったので、
翌日リベンジをしに、近くの神社で、気合いを入れておみくじを引きました。
結果は「中吉」でした。
でも、書かれてあることは結構厳しくて、
「自分の気持ちだけで行動せずに、相手のこともよく考えければ災いが起きるよ」というものでした。
ん?相手って妻のこと!?
これは、くれぐれも注意しなければ!とそう思うのでした・・・(汗)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
さて、私は、平成22年の10月から、仙台簡易裁判所で民事調停官(非常勤裁判官)を
週1回やっているのですが、先月2日に、民事調停委員の方々を対象に、1時間半ほど
民事調停について思っていることをざっくばらんにお話しました。
そこでお話した内容に少し手を加えて、みなさんにも何回かに分けてお話したいと思います。
ちょっと堅い文章ですが、よろしければお付き合いください。
=====================================
1 調停のスタンス
私は、調停には二つの軸があると思います。
一つは、調停が話し合いの場であることです。
双方当事者の合意形成をめざすところであり、当事者が相手との対話を通じて、自分で考え、自らの力で問題解決をめざし、調停委員会はそのサポート役であるというものです。
もう一つは、裁判所の考え方や判断を示すところであるというもので、
調停委員会が、お互いの言い分を聞いたうえで、調停案や17条決定を示す主体的な役割を担うものです。
この二つの軸のどちらに重点をおくかは、事案や進行状況で変化しますが、私は、後者の意識を常に根底にもちつつ、前者の合意形成サポート、当事者による自律的解決を基本とするのがよいと思います。
それは問題の解決にあたっては、誰かの意思に従うのではなく、自らの表現活動、相手との対話を通じて、自らの自由な意思決定に基づいて、問題の解決を試みるのがよいからです。
対話を通じて、合理的に物事を捉え、相手の立場や言い分も理解し、合理的な解決を自らの意思で選びとることができたらならば、その紛争は外形のみならず、心理的にも解決できたといえるでしょう。
2 話し合いの場の設定
調停の基本は、話し合いであり、当事者同士の自律的な解決を目指すということですから、当事者が安心して話し合いができる場を設定することがまずは重要です。
そのためには、まず調停委員が当事者から信頼されなければなりません。
信頼関係を築くことが大切です。当たり前のことですが、当事者の方に礼を持って接することが基本になります。
「申立人」「相手方」と呼ぶのではなく「○○さん」と名前を呼ぶこと、基本的に笑顔で接すること、そして話を聴こうとする姿勢を示すことが望ましいと思います。
話を聴いているというメッセージを送るには、「○○さんは、□□とおっしゃっているのですね」と要約できると効果的です。
心が開けば、言葉は相手の心に届きます。
心が開かないうちに、いくらいい言葉を発したとしても、相手の心には届かないものです。
理屈の正しさも重要ですが、「この人がそう言っているのなら、間違いないだろう」と信頼してもらえると、解決可能性はぐんと高くなるものです。
このような原則をおさえつつ、当事者の特性や価値観にあわせて、臨機応変に対応を変えて、信頼関係を築いていけるといいでしょう。
2 合意形成のために
(1)出発点―結論としての食い違いの確認
話し合いの最終目標は、合意形成です。
当事者双方の意思が合致したときに合意が成立し、調停が成立します。
そこで、話し合いの場にたったときの双方の主張、出発点を明確にします。
基本的には、求める結論は、申立の趣旨とそれに対する相手方の答弁で明らかにされていますので、その確認となります。
出発点として、結論の食い違いの確認をすることは簡単なことですがとても重要なことです。
申立人は、相手方に対して、いったい何を求めているのか(請求)を明確にします。
それを、相手方に伝えて、相手方がその希望に対して、どのように答えるのかを明確にします。
紛争というのは、自分の期待と相手の実際とに食い違いがある状態です。
相手が自分の思うとおりに、行動してくれない場合です。
ただ、時に、調停の前の段階において、相手に対して、何を求めるのか伝えていない場合があり、さらには、自分自身の中でも相手に対して何を求めているのか混乱している場合もあります。
そこで、調停の場において、申立人が相手に求めることを明確にして、相手方に伝えるだけで、相手も同じことを実は考えていたような場合には、その確認だけで合意形成に至ります。
申立人の請求を確認する場合には、表向きは金銭請求となっているものの、時に金額に現れない「思い」があることにも配慮が必要です。
何かの慰謝料請求事件の場合、相手に真摯に謝罪してほしい、痛みを感じてほしいといった真意があり、相手方や調停委員会から「結局お金の問題だ」とまとめられてしまうのを嫌がることもあります。
また、請求の背景にある「真意」、何のためにそれを求めているのかを探ってみると、実は食い違いがなかったこともあります。
例えば、先の場合で、相手方として慰謝料としての金銭は手元になくあまり払えないが、真摯な謝罪はしたいと思っている場合には、その真意を双方に確認することだけで、合意形成ができることもあるのです。
ですから、形式上の請求とあわせて、その「真意」を確認する作業は、話し合いの出発点としてとても重要です。
(その2に続く)
====================================
紛争の場面において、
「相手を理屈でやっつけてやろう、言い負かしてやろう」
「優秀な弁護士というのは、相手の論理の弱点を攻撃し論破して、勝利を勝ち取るもの」
そう思われる方も多いのかも知れませんね。
しかし、調停というのは、基本は話し合いであり、トラブルの円満解決を目指すところで、相手を痛めつけたり、ギャフンと言わせたりするところではありません。
トラブルが生じたときの解決方法は、暴力や威圧ではなく、対話によって解決を図るというのが、自由で公正な民主主義社会のルールです。
まずは、当事者間での話し合いです。
そして、当事者間で話し合いがまとまらなければ、中立的な第三者に間に入ってもらうのが、有効な手段となります。
昔々は、村の長老が、間に入って、話をまとめていたことでしょうし、兄弟げんかや生徒どうしのけんかなら、親や教師が間に入って、仲裁をはかるものですよね。
お話しました民事調停や弁護士会等のADRは、話し合いがこじれたときやちょっと当事者同士だけでは話し合いがしづらい状況の時などに、中立的な第三者かつ仲裁の専門家に間に入ってもらうものですから
うまく活用されれば、かなり使い勝手のよいものだと思います。
その中での話し合いは、非公開で、民事調停の調停委員もADRの仲裁人も守秘義務をおっています(他方で、裁判の場合は基本は公開の法廷です)。
話し合いがうまくいかないなあ、話し合いたいけど不安だなあとお困りの方は、民事調停やADRの活用を検討されてみてください。
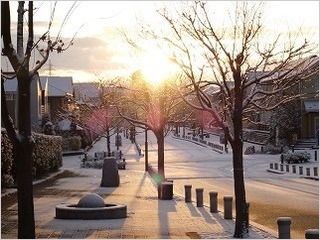
※関連のお話です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「誰が、誰に対して、いったい何を求めているのか?」
をまず明らかにすることが、調停(話し合い)では、大切だとお話しましたが、実は、自分自身の中の「対話」でも重要なことです。
ただ漫然と生きていくのではなく、
「私は、何を求めているのか?どうありたいのか?」
と自分自身に問い続け、明確にしていくことで、自らの生きる軸が定まっていきます。
自分が心の底から求めていることを明確にすること、そしてそれを表現し、実践することは、幸せに生きる上で大切なことではないかなと思います。
(やはり紙に書くことがオススメですよ!)
私もまだまだですが、自らに問い続け、できることから実践していきたいなと思っています。

それでは、また。
あなたが、幸せでありますように!
法律相談のご予約

お気軽にご相談ください。
お電話でのご予約はこちら
022-779-5431
相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで
メールでの受付は、24時間行っております(折り返しのご連絡は、基本的に上記受付時間となります)。
借金、相続、離婚、交通事故、不貞慰謝料の相談料は30分以内無料です。その他の事件は、30分あたり5500円です。
※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。
※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。
※取扱い地域
仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域
無料法律相談のご予約
コラム
- バーガー国ものがたり~3つのアイデア:自然権、社会契約、法の支配
- 他人と比べないこと(R3.11.15)
- 生きがいについて(R2.11.23)
- 所有権絶対の原則!(R2.4.6)
- 長男の妻の労苦は報われるのか?(R2.4.2)
- 配偶者居住権が新設されました(R2.4.1)
- パワハラをしないためには知識が必要です!(R2.3.25)
- こども六法(R1.9.24)
- 国民主権って何だろう?(R1.7.15)
- 裁判官はどのように判断しているのか?(R1.7.6)
- 自分の主観と相手の主観とはズレているもの(R1.6.30)
- 本当に怖いセクハラパワハラ問題(R1.6.22)
- 愛の本2 自分以外の人は全て他者(H31.2.10)
- 愛の本 他者との〈つながり〉を持て余すあなたへ(H31.2.3記)
- 自分の一番の味方は自分(H31.1.21)
- 友だち幻想3 人生の苦味・うま味(H30.9.9)
- 対人距離がわからない(H30.8.6)
- 正義とは他者に対する公正さ(H30.7.15)
- 人間関係に悩んだら、とりあえず「登場人物」を紙に書きだす(H30.6.12)
- 友だち幻想2 距離の感覚(H30.5.29)
- 友だち幻想 人と人のつなばりを考える①(H30.5.14)
- 主観的に大切なこと、客観的に重要なこと(H30.5.3)
- 自己開示の効用(H29.12.23)
- 人生は思うようにはならないもの(H29.9.21)
- 正義って何?~反転可能性テスト(H29.9.16)
- 悩んだら、とりあえず散歩(H29.6.25)
- 自分に価値があると思えるために2(H29.4.27)
- 自分に価値があると思えるために(H29.3.5)
- 3人のレンガ職人(H28.9.26)
- よく生きるために働くということ(H28.9.18)
- 弘前の桜(H27.5.8)
- 取引先破綻の商品引き上げについて
- ずっと運の悪い人はいませんよ。
- 第○回の調停を始めます! (H26.8.30)
- 複数のスポーク
(H26.8.14) - 嫉妬心とのつきあい方(H26.7.27)
- 本当は仲直りがしたいのに (H26.6.15)