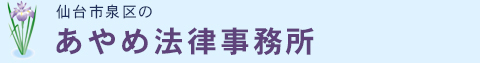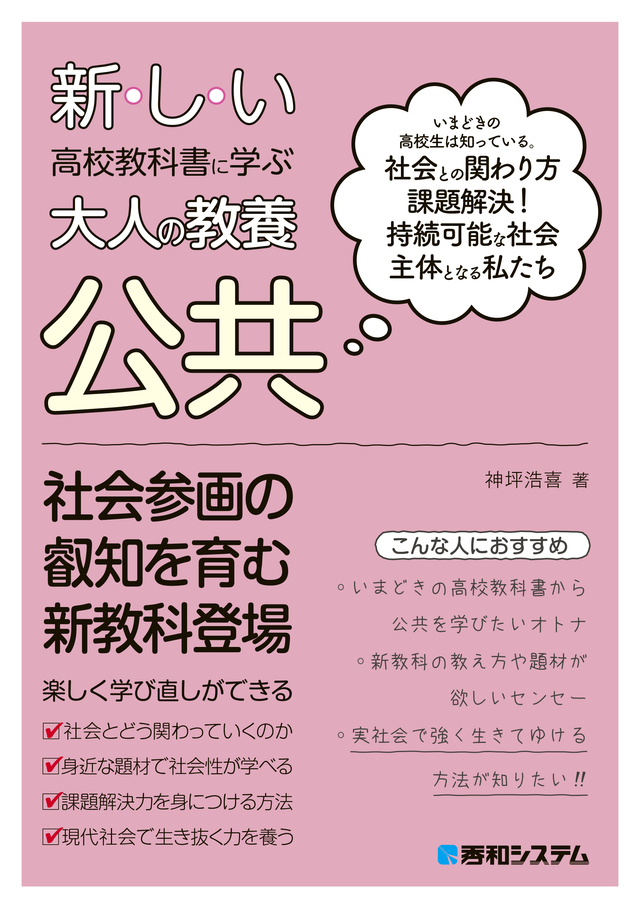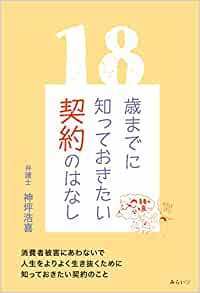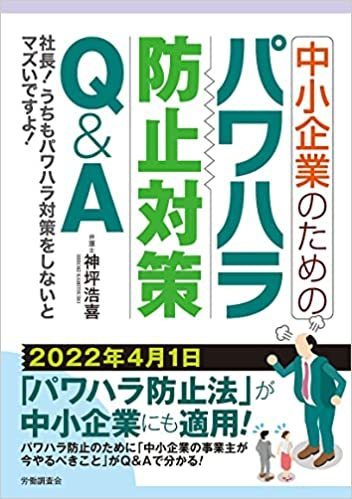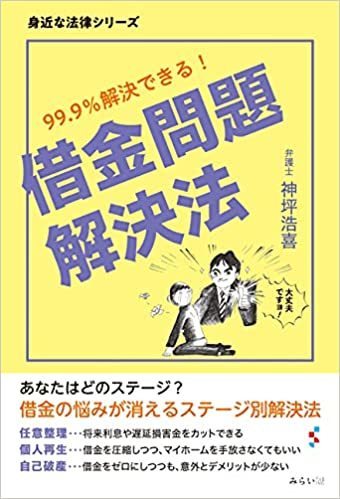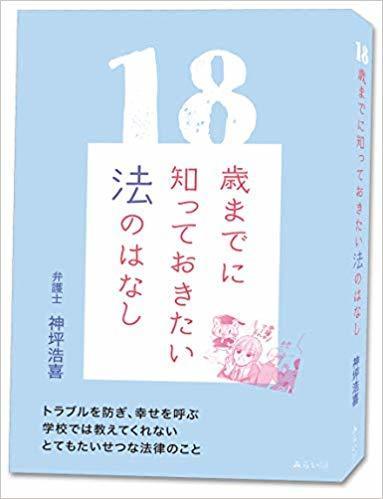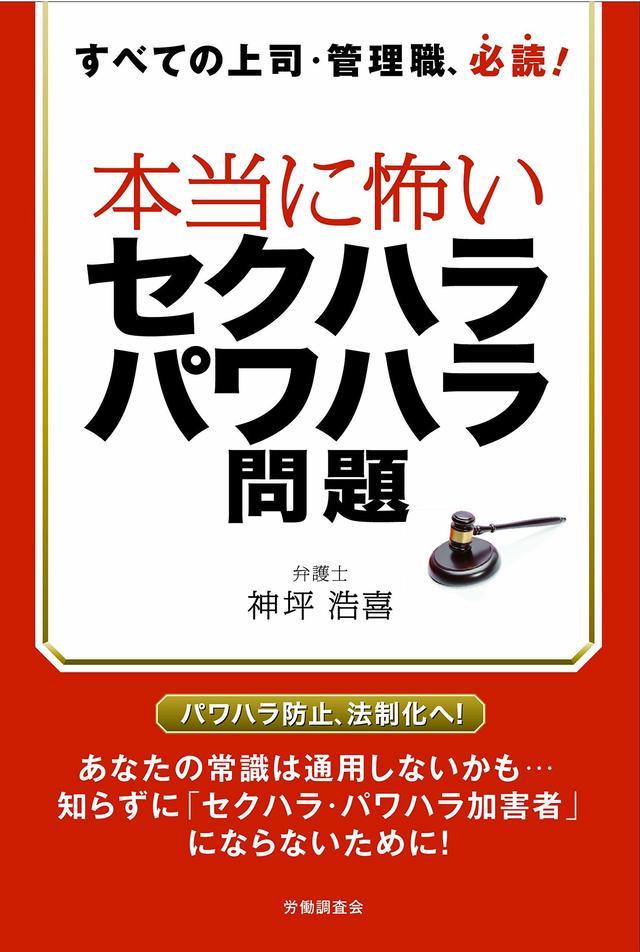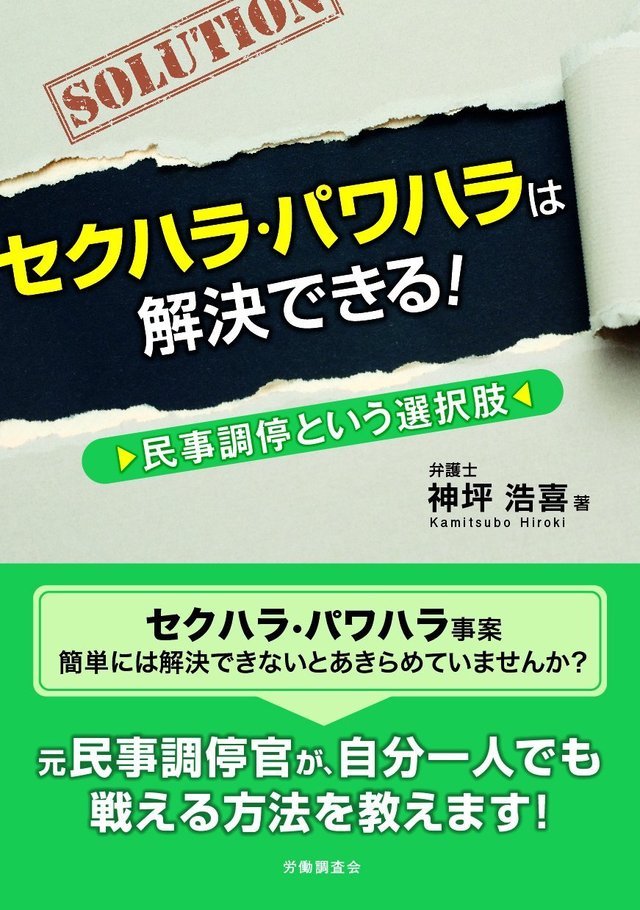宮城県仙台市泉区・地下鉄泉中央駅徒歩4分の「あやめ法律事務所」では、3名の弁護士が、借金・離婚・不倫・相続・交通事故等の無料法律相談を実施しています。
<お電話での相談受付時間>
平日 午前9時30分~午後0時20分
午後1時20分から午後5時15分まで
メールでは24時間受付
法の支配-罪刑法定主義2
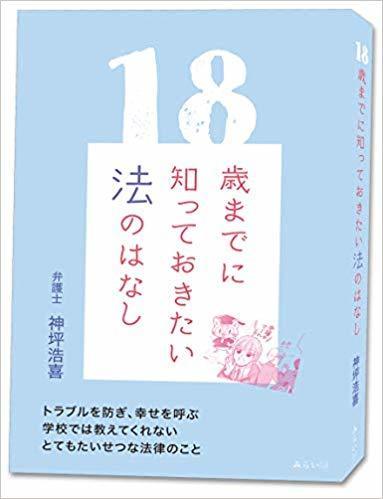
罪刑法定主義についてのお話です。
罪刑法定主義については、このブログでも以前、少し触れました。
以前、憲法の核心は、13条、個人の尊厳、つまり一人ひとりを大切にすることにあるとお話しました。
主体(「誰が」大切にするか)は、国家であり、
客体・対象(「誰を」大切にするか)は、国民一人ひとりです。
「国家が、国民一人ひとりを大切にせよ」と憲法は、国家にむけて縛りをかけているのです。
それは、国家が、その強大な力から、国民の権利自由を奪うとダメージが大きく、現に、過去に国家の利益を優先して、国民一人ひとりの自由を踏みにじってしまった歴史を深く反省してのことでした。
国家権力を行使するのは、現実には、人、国会議員や公務員です。
警察官、検察官、裁判官、県庁や市役所、税務署の職員等です。
そこで、憲法は、権力行使に携わる人に対して、「憲法を尊重し擁護する義務を負う」と定め(日本国憲法第99条)、「憲法をちゃんと守ってね」つまり「国民一人ひとりの権利自由を、侵害しないように気をつけてね 。」と注意しているのです。
国家権力の行使において、国民の権利自由を制限することがあります。
その権力行使において、公務員が、好き勝手に国民の権利自由を制限をしてもよいでしょうか。
例えば
警察官が、街で、道に落ちていた財布を拾った人を偶然みかけ、「お前、ネコババするつもりだな!」といきなり警棒でなぐって逮捕したらどうでしょうか。
県庁の職員が、突然やってきて、「ここを県道が通ることになったから家を撤去する」
なんて言って、あなたの自宅をいきなり壊しはじめたらどうでしょうか。
裁判官が、今日は奥さんとけんかして機嫌が悪いからといって、適当な裁判をして、被告人に重い判決を下したらどうでしょうか。
怖いですよね。
もちろん、今の日本の社会では、ここまでのことは起きません。
それは、どうしてでしょう。
それは、公務員が、その権力行使をする際、国民の権利自由を制約する場面においては「法律」に従って行動しているからなのです。
法律の根拠に基づいて権力行使をしているからなのです。
法律に基づかないということ、それは、権力行使をする人の好き勝手にできること、気分次第になってしまうこと、権力行使をする人次第になってしまうことを意味します。
そういう世界を「人の支配」といいます。
そんな世界ってとても怖いですよね。
でも、昔はそんな時代があったのですよ。
しかし、現代社会は、「人の支配」ではなく、「法の支配」なのです。
現代社会は「法治国家」と呼ばれています。
法律によって、権力行使がなされる場合を定めておいて、権力者が好き勝手に、国民の権利自由を制限できないようにしました。
また、同じ条件のもとでは、同じ権力行使がなされるようにしました。
つまり、同じような悪いことをすれば、悪いことをした人の人種や思想、性別、どんな仕事をしているか等にかかわらず、法律の定めた手続にしたがって、法律の定めた範囲内の刑罰を受けるのです。
政治家であろうが、サラリーマンであろうが、主婦であろうが、大富豪であろうが、ホームレスの人であろうが、すべて法の下では平等なのです(法の下の平等)。
もし、人を怪我させれば、法の定めた手続にのっとって、法の定めた範囲内で処罰されるのです。
もちろん、法律の定めには、幅があり、枠組みだけを決めていることもあり、具体的な権力行使の場面において、行使する公務員の裁量が働くことはありますが、法律の枠があることによって無茶苦茶な権力行使、国民の権利自由が理不尽に奪われることが抑制されるのです。
それが、「法の支配」の理念です。
権力行使する人の人次第にしないように、権力行使者の感情や思いこみ、好き嫌いに左右されないように、法というみんな(国民の代表者)で決めた理性的なもので、コントロールすることで国民一人ひとりの権利自由が、国家権力から不合理に奪われないようにしているわけです。
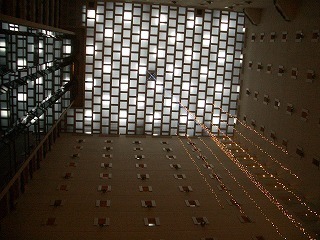
国民一人ひとりの権利自由が、国家から、最も制約される場面とは、一体どんな場面でしょう。
そうですね。刑罰を受ける場面ですね。
自由や財産を奪われ、場合によっては、今の日本では、命まで奪われるというのが刑罰です。
ですから、国家には、適切にその刑罰権を行使してもらわなければなりません。
間違って無実の人に刑罰を科したりすることが絶対あってはなりません。
また犯罪を犯した人であっても理不尽に重い刑罰であってはなりません。
刑法という法律があるということは、多くの方が知っておられるかと思います。
犯罪と刑罰を定めた法律ですね。
「○○のことをしたら、□□の刑罰に処する。」
といろいろな犯罪について定められています。
例えば、人を怪我させたら、傷害罪ということで
刑法204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
の規定が問題となってきます。
刑法というのは、国家が、国民を取り締まっているような感覚を持ちますよね。
もちろん、刑法は、犯罪という他者に酷く迷惑をかける行為について、その犯罪行為をしたら、処罰するぞとして、国家が犯罪を防止しようとしたり、犯罪行為をした人にきちんと適切な罰を受けさせることで秩序を維持しようという、国民にむけられたものではあります。
国民の中には、人を怪我させると、こんな刑罰を受けることになる、罰を受けるのは嫌だから怪我させないようにしようと思う人もいるでしょう。
でも、刑法という法律を定めたことの、大事な視点がもう一つあるのです。
ほとんどの方が、気が付かない、意識しない視点があるのです。
一体、何でしょう?
それは、「法の支配」の視点です。
つまり、刑法という法律が、権力行使者(裁判官、検察官、警察官)に対して、「権力行使は、この法律にもとづかなければならない。」「法律に定めていない権力行使はしてはいけない。」と縛りをかけていることです。
だから、裁判官は、人を怪我させた被告人が全然反省していないのをみて、「こいつはけしからんから厳しく処罰してやろう」と思って、死刑判決や無期懲役判決を下すことはできません。
また、警察官が、電車内で携帯電話をかけている人をみかけて、「マナーがなっとらん!」と思って、逮捕することはできないのです。
なぜなら、そこには法律の根拠がないですから・・・
罪刑法定主義、つまり、何が犯罪にあたり、どのような刑罰が科せられるかをあらかじめ定めておかなければならないということは、国民一人ひとりの権利自由が、国家権力から、理不尽に奪われないようにしておくための「法の支配」の理念から導かれるとても大切な原則なのです。
あらかじめ犯罪と刑罰を法律で定めておかなければならない、法律の定めがなければ、処罰されないといことで、国民は、どういうことをすれば犯罪として、どんな処罰がされるのか、逆に、どういう行為なら犯罪にならずに処罰されないかということが分かります。
ですから、憲法は明文をもって「罪刑法定主義」を定めます。
日本国憲法第31条
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」
今日のお話では、
個人の尊厳確保(国家が、国民一人ひとりを大切にする)
↓
国家権力(特に刑罰権行使の場面)
が理不尽・不適切になされると個人の尊厳が踏みにじられる
↓
そこで、「法の支配」、「罪刑法定主義」
で、国家権力が恣意的に理不尽に行使されないように、権力行使を法に基づかせる
ということを是非理解しておいてくださいね!
それでは、また。

【出版のお知らせ】
法について、私がわかりやすくお話しした「18歳までに知っておきたい法のはなし」(みらいパブリッシング)が、好評発売中です。立憲主義や国民主権、権力分立といった憲法のこと、契約のこと、犯罪と刑罰のこと、交渉のこと、法的なものの見方考え方のこと、とにかくわかりやすく書きました。ぜひ、ご覧になってみてくださいね!!
Amazonのページはこちら
(目次)
はじめに
第1章 そもそも法って何?~いろいろな人がいる社会の中で幸せに生きる仕組み
1 法と幸せ
2 ルールはなぜ必要?
3 よいルールの条件とは?
4 正義って何?
コラム)桃太郎は正義の味方か?
第2章 僕たちは憲法のもとに生きている
1 民主主義と立憲主義のはなし
(1)民主主義って何?
(2)民主主義って多数決のこと?
(3)憲法は、国家を縛る~立憲主義
(4)表現の自由がない世界
(5) 民主主義と立憲主義-個人の尊厳をまもる
2 権力分立~権力の濫用を防ぐためのシステム
3 ジョン・ロックのはなし~国家、自然権、法の支配
4 国民主権って何?
(1)主権が国民にあるってどういうこと?
(2)18歳になったら選挙権行使!
5 基本的人権の尊重~憲法は人権のカタログ
第3章 裁判員になっても大丈夫?~刑事手続
1 弁護士はなぜ「悪い人」の弁護をするの?
2 逮捕されてしまった!その後どうなる?
3 犯罪と刑罰のはなし
(1)犯罪って何だろう?
(2)どんな刑罰があるのだろう?
(3)死刑制度について考えてみよう
(4)なぜ刑罰が必要なのだろう?~刑法の目的
4 刑事手続
(1)いきなり「刑務所行き」にはできない
(2)なぜ、被疑者、被告人には黙秘権があるの?
5 検察官の役割
6 弁護人の役割
7 無罪推定の原則~疑わしきは被告人の利益に
8 もしも君が裁判員に選ばれたら~裁判員として知っておきたいこと
(1)裁判員とは?
(2)裁判員になるまで
(3)裁判員として審理に立ち会う
証拠に基づく事実認定を行う
量刑~被告人に言い渡す刑をどうする?
第4章 大人になる前に知っておきたい契約・損害賠償のこと~契約、市民生活に関する法
1 契約って何?
2 どんな契約も守らないといけないの?
(ア)契約の拘束力にも例外がある
(イ)契約を解約できる場合
1)未成年者取消権
2)詐欺取消、強迫取消
3)債務不履行契約解除
4)合意解約
5)クーリングオフ
3 悪徳商法に騙されないために
1)ワンクリック詐欺
2)デート商法
3)マルチ商法
4 借金を返せなくなったらどうなる?
(1)お金を借りることの意味
(2)友達から「保証人」になってと頼まれたら
(3)もし借金に困ったら
5 働くときのルール ワークルール
(1)立場が弱い従業員を守るワークルール
(2)働く前に知っておきたいワークルール
1)労働時間
2)賃金
3)休暇
4)解雇のルール
(3)ブラック会社に気をつけよう
(4)セクハラ・パワハラで困ったら
6 損害賠償のはなし
(1)どんなときに損害賠償請求ができるのか?
(2)「損害の公平な分担」という考え方
第5章 交渉法を身につけよう!
1 交渉って何?
2 交渉のコツ
(1)準備が大切
(2)交渉の場で
①感情的にならずに冷静に伝える
②論理的に伝える
③相手の言い分をきく
④自分の言い分と相手の言い分とを整理する
⑤解決案を考える
第6章 トラブルに巻き込まれたら
1 弁護士に相談してみる
弁護士の探し方
いい弁護士の見分け方
2 調停というもめごと解決法もある
第7章 裁判所ってどんなところ?
1 裁判の役割
2 裁判傍聴に行ってみよう
3 裁判官という仕事
(1)裁判官の責任は重大
(2)裁判官ってどんな人?
(3)裁判官のやりがい、苦労
第8章 法的なものの見方・考え方を身につけよう!~大人の知的技能
1 主張(意見)に理由をつける
2 事実と意見を分ける
3 事実の中で、どういう事実が重要になるかを見極める
4 事実については、裏付ける証拠がないかを確認する。
5 論理的思考とは
おわりに
「個人の尊重」-何かを大切に思う気持ちに違いはないこと
法律相談のご予約

お気軽にご相談ください。
お電話でのご予約はこちら
022-779-5431
相談受付時間:平日 午前9時30分~午後0時20分、午後1時20分~午後5時15分まで
メールでの受付は、24時間行っております(折り返しのご連絡は、基本的に上記受付時間となります)。
借金、相続、離婚、交通事故、不貞慰謝料の相談料は30分以内無料です。その他の事件は、30分あたり5500円です。
※法テラスの扶助相談が利用できる方は、そちらをご利用していただく形になります。
※お電話やメールでの相談は実施しておりませんので、ご了承ください。
※取扱い地域
仙台市、富谷市、大和町、利府町、大崎市その他宮城県全域
無料法律相談のご予約
コラム
- バーガー国ものがたり~3つのアイデア:自然権、社会契約、法の支配
- 他人と比べないこと(R3.11.15)
- 生きがいについて(R2.11.23)
- 所有権絶対の原則!(R2.4.6)
- 長男の妻の労苦は報われるのか?(R2.4.2)
- 配偶者居住権が新設されました(R2.4.1)
- パワハラをしないためには知識が必要です!(R2.3.25)
- こども六法(R1.9.24)
- 国民主権って何だろう?(R1.7.15)
- 裁判官はどのように判断しているのか?(R1.7.6)
- 自分の主観と相手の主観とはズレているもの(R1.6.30)
- 本当に怖いセクハラパワハラ問題(R1.6.22)
- 愛の本2 自分以外の人は全て他者(H31.2.10)
- 愛の本 他者との〈つながり〉を持て余すあなたへ(H31.2.3記)
- 自分の一番の味方は自分(H31.1.21)
- 友だち幻想3 人生の苦味・うま味(H30.9.9)
- 対人距離がわからない(H30.8.6)
- 正義とは他者に対する公正さ(H30.7.15)
- 人間関係に悩んだら、とりあえず「登場人物」を紙に書きだす(H30.6.12)
- 友だち幻想2 距離の感覚(H30.5.29)
- 友だち幻想 人と人のつなばりを考える①(H30.5.14)
- 主観的に大切なこと、客観的に重要なこと(H30.5.3)
- 自己開示の効用(H29.12.23)
- 人生は思うようにはならないもの(H29.9.21)
- 正義って何?~反転可能性テスト(H29.9.16)
- 悩んだら、とりあえず散歩(H29.6.25)
- 自分に価値があると思えるために2(H29.4.27)
- 自分に価値があると思えるために(H29.3.5)
- 3人のレンガ職人(H28.9.26)
- よく生きるために働くということ(H28.9.18)
- 弘前の桜(H27.5.8)
- 取引先破綻の商品引き上げについて
- ずっと運の悪い人はいませんよ。
- 第○回の調停を始めます! (H26.8.30)
- 複数のスポーク
(H26.8.14) - 嫉妬心とのつきあい方(H26.7.27)
- 本当は仲直りがしたいのに (H26.6.15)